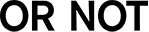TOLD BY TOSHIKO TAGUCHI RECALL: RAF SIMONS 3
『MRハイファッション』の編集長が出会ったデザイナー。 「トリエステでラフにかけられた、本質をつく優しいひと言」
ラフ・シモンズとの記憶を巡って『MR』と『ハイファッション』をめくるうちに、田口さんが2005年から5年連続で訪れた、イタリア・トリエステで毎年7月に開催される“滞在型”のファッションコンテスト「ITS(International Talent Support)」の話題に移っていった。イタリアの東北端。ヴァネチアの東側に位置し、スロベニア共和国とも隣接するアドリア海に面するトリエステは、「海をへだてて、イタリアにいながらイタリアを眺望できる」港湾都市だ。『ハイファッション』では、毎回8月発売の10月号で、多くの写真とレポートとで「ITS」を紹介してきた。
「いつも3泊5日で訪れていたトリエステは、人口20万人程の小都市。須賀敦子さんに『トリエステの坂道』という著書がありますが、その坂道の至るところに連なる住宅や教会などの建造物を見ていると、ここは純“イタリア”だとは言い切れない、長い歴史の層を感じ取ることができます。コマーシャリズムやスノビズムとは無縁の場所で、『ITS』の関係者たちも皆、夏休みのようなリゾートライクでラフな装いをしています。ゲストとして訪れていたウォルター・ヴァン・ベイレンドンクやダーク・ビッケンバーグと、港に面した広場にある貸切りのレストランで、ランチの時に出会ったりすることもありました。主催者であるディーゼル社の創始者レンツォ・ロッソの『ITS』のヴィジョンは、“皆がリラックスした時間を楽しみながら”コンテストに臨めることと、実に悠揚としているのです」
ロンドンのセントラル・セント・マーチンズやアントワープ王立芸術アカデミーといった世界中のファッションスクールに在学中の、あるいは卒業して間もないコンテストの最終選考に選ばれた若きデザイナーたちと、時間を気にせず朝から深夜まで交流することができるのだという。「ファイナリストたちは、プレゼンテーションでインタビューに答え、世界各地から来たジャーナリストやデザイナーとフレンドリーな時間を共有してネットワークを広げる好機を得ることもできる。多様な国籍のファイナリストの中には、山縣良和さん、坂部三樹郎さん、堀内太郎さん、中里唯馬さんといった日本人もいました。現在は内外で活躍している多くの日本のデザイナーたちと、彼らがまだ在学中か卒業前後といった頃に、トリエステで初めて出会ったのです」
田口さんにとって2度目の滞在となった2006年の「ITS#FIVE」で、ディーゼルジャパンの広報担当者やカメラマンとともに、最終審査が行われる会場のリハーサルの様子を見るべく海岸沿いを歩いていたとき、ちょうど会場から出てきたラフ・シモンズとばったりと遭遇して10分ほどの立ち話をしたという。彼はこの年の審査員のひとりとして招聘されていたのだ。
「ラフとは、東京以来の偶然の再会でした。私は疲労と寝不足が続くと、左目の同じ部分の毛細血管が切れて赤く内出血してしまうのが長年の癖になっていて、出国の前日にまたしても再発。医師に、赤みは薬では治せない、自然回復を待つしかないと言われてかなり落ち込んでいたのです。同じ場にいるほかの人たちに赤い目で不快な思いをさせたくなくて黒いサングラスをしていたのですが、その日、ラフとの思いがけない出会いで思わず外してしまったのです。私の真っ赤な目をみたラフは、開口一番、『僕も疲れるとすぐそうなる。同じだね』と言ったのです。通常なら初めに『大丈夫?どうしたの?』という言葉が出てきそうな場面で、ラフは『自分も同類だから、気にしないで』と語りかけてくれて、できるなら人とあまり会いたくないという私のネガティヴな気分を、たった一言で払拭し、楽にしてくれたのです。たまたまラフも同じような体質だったのでしょうが、社交的な挨拶の会話ではなく、本質をついた言葉による優しい配慮に触れて、以後は滞在中、目を気にすることなくのびのびした気持ちで過ごすことができました。おそらく彼は、ものづくりにおけるスタッフとのコミュニケーションにおいても、過剰に言葉を費やすのではなく、他者と並列に立ち、シンパシーや本質的な優しさを実感できる対話で、人の気持ちを前向きにしながら、チームワークとしてのクリエイションを牽引しているのではないか。ラフならではの気質を確信させるものが、あの一言にはありました」
ラフが、ジル・サンダーにおいて信頼関係を重視していることが窺い知れる『ハイファッション』でのインタビューがある。「デザイナーは、一人では何もできない」と語りながら、1970年代からジル本人と仕事をしてきた自分より年上のアトリエの職人への敬意と感謝を示しながら話していた。「彼女たちはオープンで、高い教養を持ち、文化に精通しているので、私が『ポル・シャンボスト』と投げかけても、瞬時にそれが何かを理解し、そのように対応すべきかわかってくれた。彼女たちは年下の私を受け入れてくれ、いろいろなことを教えてくれました」(引用抜粋)。田口さんが特筆すべき成果という2009-10年秋冬のレディスコレクションを終えた後の言葉だ。
「陶芸家ポル・シャンボストの花器から発想を得た、ウエストを絞ったシンプルの極致と言えるコートドレスやワンピース、アシンメトリーにフレーミングされた襟のフォルム……。工業デザインの素養があり、無類のアート志向と、文化への教養の深さでも知られるラフが、ジル・サンダーを手がけることの意味が今シーズン結実したと、私は感じたのです」
田口さんは、ジル・サンダー本人が一貫してきた“素材から始める”というクリエイションのスタイルに、ラフは決定的に合意していたことに言及しながら、「柔らかいオーガンジーやフューチャリスティックなファブリックを取り入れたり、長いフリンジを全身に用いたりと、かつてのジル・サンダーにはなかった素材使いと職人との対話を軸に、ラフの嗜好性がベースにある“実験”を2005年の就任以来ゆっくりと繰り返してきたのではないか」と語る。
「熾烈なモード界で、デビューからの4~5年というのはとてつもなく長い時間なのです。私は、ラフのコレクションを見続けてきて、かつてジル・サンダー本人にインタビューをしたときに彼女が語った『long time thinking。それが私のクリエイションの方針なの』というコメントに深く頷いたことを思い浮かべました。それはラフのスタンスとぴったりと合致するように思えた。アトリエのスタッフの力を最大限に引き出して、就任してから4年後には、花器のような息を呑むフォルムのドレスを作り出したのです。ラフは、ジル・サンダーのクリエイティブディレクターとしてコレクションを重ねるごとに、“ジルらしさ”のエッセンスを見抜きながらも、急激にではなくじわじわと、アートという彼の抜きがたい嗜好性を融和させていった。つまり彼もまた、紛れもなく『long time thinking』の人だったのです」
田口淑子 Toshiko Taguchi
1949年生まれ。『MRハイファッション』と『ハイファッション』の編集長を務め、現在はフリーランスのエディター。
Text_ TATSUYA YAMAGUCHI