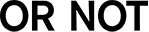TOLD BY TOSHIKO TAGUCHI RECALL: RAF SIMONS 4
『MRハイファッション』の編集長が出会ったデザイナー。 「深い共鳴が、“同質”の人を呼び寄せるモード」
「ラフと最後に会ったのは、2011年10月に国立新美術館で開催されたジル・サンダーのショーの後、中二階で行われたアフターパーティの場でした」。すでにミラノで発表されていた2012年春夏コレクションが、レディスとメンズの合同ショーの形式で披露されたのだ。
「あの夜は、多くの人に囲まれたラフとほんの少し挨拶を交わす程度でした。具体的な“ピカソの顔”が描かれたニットをみて、率直に言うととても意外でした。過去には、イヴ・サンローランのモンドリアンルックなどに代表されるように、アートが直接的にわかりやすく服に引用されてきた例があります。これらは時代に呼応し、融合しやすかったのだと思います。一方、こうしたアートとモードを融合させる直裁的な表現は、ラフでなくてもいい、他人に任せておけばいいのに……というのが私の本音でした。これは、叶うなら今でも彼に『どうして?』と尋ねてみたいこと。ショーの後、こうしたストレートなアプローチではない、“ラフらしさ”の表現をみてみたいと感じていたのです」
その、“ラフらしさ”を巡りながらも、田口さんが2010年に文化出版局を退社する以前の、在職中(雑誌部長兼『HF』のエディトリアルディレクター時)より非常勤講師を勤めていた早稲田大学での講義の一コマに、話題が移った。「さらす/覆うの構造学」という講義名をキーワードに、建築家やフラワーアーティストといった専門分野のプロフェッショナルが数週間ごとにゲスト講師として招かれる、オムニバス形式の授業だった。受講者の中心は、哲学や社会学、ジャーナリズム、舞踏といった幅広い領域の講義がある、文化構想学部の学生。田口さんは、ファッションとファッション誌をメインテーマに5年間継続して講義を行ってきた。
「この講義中、聴講生が目で具体的に確認できるヴィジュアルとして、『MR』や『HF』のページをスクリーンに映すことも多く、トークの内容にそって映像を上映することもありました。たとえば、パリとロンドンを往復するポール・スミスさんの日々を追ったドキュメンタリー、堀内太郎さんが自身のコレクション発表のために制作した映像など。そして、2012年の、私の最後の講義の担当回で学生に観てもらいたいと迷わずに決めたのが、ラフによる、最後のジル・サンダーのコレクション、2012-13年秋冬レディスのランウェイショーでした」
「15分程度のショーをパソコン上の映像で観ても感じとるものがあまりに少ないので、普段は最後まで観ることは少ないのですが」と田口さんはことわりながら、「あのショーには深い感銘を受け、何度も何度も見返したのです」と、10年前の記憶を手繰り寄せていた。「5年間の講義経験から、文化構想学部には複合的なものの見方ができる学生が多く、服そのもの、モデルの歩き方、ヘアメイク、装置、音楽、空間を含めた総合性の中から、各々が何か感じ取るものがきっとあるだろうという期待がありました。一方で、私にとっては最上質なこのショーと対峙した時の、ファッションとは縁遠いヨレたTシャツを着ている一部の学生たちの反応を確かめてみたいという思いもありました。もし、250人ほどの学生の中で、退屈して飽きたり、あくびをするような人が目立ったら、途中でショー映像を止めてトークに戻ろうと、当時の講義のアシスタントと打ち合わせをして、彼らの表情を観察していました。そんな懸念を裏切るかのように、暗転した教室はすぐにシーンと静まり、うたた寝しそうだった学生までもが顔を上げてスクリーンにじっと観入っているのです」
講義終了後に受講生が書いて提出するレビューシートの中には、涙が出てきたという学生もいたという。「洋服と音楽、空間、人の佇まいの、観たことのない調和に驚いた」「空間美に圧倒された」「洋服ではなく、まるで舞台や、短編の映画を観ているようだった」。これまでファッションショーを観たことのないだろう学生からの、感動を伝えるピュアで素直なリアクションがあったことを田口さんはよく覚えているのだと教えてくれた。
「バレリーナのような引っ詰め髪のモデルが、花を封じ込めた柱のオブジェの間を回遊魚のように歩いていく。ディテールデザインがほとんどないビスチェドレスや、忘れがたい所作でもある、胸元を片手でクシュっと握った、ノーカラーの、フォルムだけでみせるカシミヤのコートは、ベーシックなジル・サンダーの“基本”を想起させるものでした。特筆すべきは色。ピンク嫌いでもある私が着たいと思う、ヌーディピンクやペールブルー、ブラック、ホワイト、ベージュもまた、いわゆる、淡彩とは言い切れない、どれもが独自に抽出された、深く、魅力的な色でした。さらに、あの空間で、細いストラップや胸の切り替えだけで表現されていたのは、セクシーさではなく、気品や荘厳さ、あるいは禁欲性という、外見とは逆説的なエレメントでもあった。90分間の講義のうちの最後に流そうと決めたのは、こうしたことを内包したこのシーズンのアイテムは、オートクチュールのように特殊な服ではなく、より“クリエーションの力”を感じ取ることができるものだという確信があったから。ラフが、ジル・サンダーで長い月日をかけて作り上げた“本当の贅沢としてのシンプル”は、装飾性を削ぎ落としても、内側にはたわわな感情がこもっている。クールにみえて、わずかな人の内面には共鳴する、熱気がある。あるいは、言葉に置き換えることが困難なものでもある……。このコレクションは、聴講者全員ではなくとも、たとえば、ほんの一割の学生にとって、彼らのこれからのファッションの志向の可能性を誘引するものであったと思っています」
田口さんは、20歳のころに手にしたという、埴谷雄高の著書『闇のなかの黒い馬』(挿画は駒井哲郎)を書棚から取り出して、「ラフの特質を捉えることをこのタイトルになぞらえるなら、『闇の中にいる黒い馬を観ることができるか?』という問いに言い換えることができるのではないか」と、話を続けた。
「ラフは、ジルの“シンプリシティ”の中にある、さまざまな表情を透視していたのでしょう。それは、思索的、思惟的な行為だと言ってもいい。ディオールに移ったラフの、最初のオートクチュールのコレクションも、ムッシュ・ディオールのフォルムをはっきり透視できるとともに、ニュールックに代表される“あの時代のモード”が、ラフのクリエーションと“二重写し”になって、見事な融和を見せていました。あるいは、ミウッチャ・プラダの眼が、ブランドの未来を見据え『この人だ』と確信し、同質の存在としてラフを迎え入れたことにも、通ずるのではないでしょうか。“数”の多さとは対極的な、“質”の深度の一致という幸福な出逢いは、同質の人と人が引き寄せられたり、呼び寄せることからはじまる。これは、定理なのではないかと思います。ラフとジルもそうであったに違いありません。そうして生み出された比類のないモードに、私もまた呼び寄せられるような感動を覚えてきたのです」
田口淑子 Toshiko Taguchi
1949年生まれ。『MRハイファッション』と『ハイファッション』の編集長を務め、現在はフリーランスのエディター。
Text_ TATSUYA YAMAGUCHI