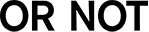TOLD BY TOSHIKO TAGUCHI RECALL: JOHN GALLIANO 1
『MRハイファッション』の編集長が出会ったデザイナー。 「オートクチュールという名の芸術で、観客を陶酔させたジョン・ガリアーノ」
1970年代からファッションショーを観続けてきた田口さんに、今なお、その光景を鮮明に思い出すことのできる稀有なショーがあったかを尋ねた。まだ20代のころに観たという、山口小夜子さんが舞うようにして舞台に登場した70年代のケンゾーには、服と音楽とモデルとが一体になっていて今も忘れることのない、賢三さんならではの詩情があったと語りながら、五指に数えるショーとして抜き難いのは、ジバンシィのオートクチュール(1996年春夏)だという。「創始者のユベール・ド・ジバンシィから引き継いだばかりの若きジョン・ガリアーノが、初めて手がけるオートクチュールを観るという幸運に恵まれたのです」
「私は、10代後半の、まだ編集者として働く以前から、土方巽さん、大野一雄さん、笠井叡さん、3人の舞踏家の舞台に瞠目してきた。強いていえば人を、観た人と観ていない人に分類できるほど、私にとってその舞台体験は決定的でした。後の、様々な舞台を見極める上での基準になっているとも言えます。その頃、ファッションショーのステージは、ほとんどの場合はプロローグだけ。何かが始まりそうなのに何も始まらないであっけなく終わってしまう。服だけに着目すればその限りではありませんが、序章だけの舞台に失望することが多かったのです。しかし、パリ郊外のサン=クルーにある古く巨大な体育館の三方に四角い舞台を作り、がらんと広いフロアをモデルが回遊していたガリアーノによるショーは、ソワレを纏った一人ひとりが物語の主役を担っているようで、壮大な無言劇を観ている気持ちになったのです。モデルの所作や佇まい、歩き方にいたるまで、ガリアーノ自身による綿密な指示だったのではないでしょうか。服と空間、構成、演出などのすべてをクリアし、観る者にドラマ性を喚起させる、一度見たら決して忘れることのできない至高の芝居空間、芸術空間とも言えるものでした」
1996年からの約2年間、田口さんは『MR』のみならず、『HF』の編集長を兼任していた。「『パリメンズのすぐ後なのだから、時間がないなんて言わないで一度はオートクチュールを観てきなさい』と上司に言われたのです。メンズ誌を長くやっていて、また、自分の着られる服ではないという非現実感もあってオートクチュールには無関心だったのです。が、初めて目の当たりにしたオートクチュール・コレクションは予想をはるかに超えて美しかった。『MR』のレイアウトを一任し、その審美眼に信頼をおいていたADは、パリから届いたジバンシィの写真の数々に珍しく感嘆し、完成したページをみた若いスタッフは、ガリアーノのドレスの美しさに無言で見入っていました」
巻頭の、ガリアーノの手によるすみれの花の色のガウンドレスで、7~8メートルはあるトレーンをひいたモデルの後ろ姿が圧巻な、『HF』の1996年5月号のオートクチュールの特集を開いた。1996年春夏で発表された全約20のメゾンのコレクションを偏向なく紹介しながらも、クリスチャン・ラクロワと、当時ジャンフランコ・フェレが手がけていたクリスチャン・ディオール、そしてガリアーノによるジバンシィの3メゾンを中軸においた誌面からは、ショーを目撃した時の田口さんの感動がそのまま伝わってくるようだった。田口さんは同号の編集後記に、「オートクチュールは、服がきちんと着目させずにおかない力を持っている」と書き添えていた。
同特集の冒頭に、「8番めの芸術、オートクチュールは続く。」と題したテキストがある。プレタポルテ(高級既製服)の浸透と、経済危機によって、100年以上の歴史をもつ伝統的なオートクチュールの存在意義が、とりたてて“フランス外”のジャーナリストらから危ぶまれていることに言及しながらこう書き記されている。「フランスでは映画を“7番めの芸術”と言うが、オートクチュールは“8番めの芸術”と呼んで(諸説あり)手仕事のすばらしさをたたえる。そしてオートクチュールの職人は、日本でいえば人間国宝にたとえられる」
田口さんは、「この、モードを文化として、芸術として捉えるフランス人特有の美学に基づいた文言に深く同意したのです」という。「ジバンシィのショーで、贅沢なディテールを生み出すオートクチュール職人の手仕事の温度と、凄みを感じながら、その場に遭遇して体感できることは編集者の特権なのだと改めて感じたことを覚えています。その実感を、どのように誌面にするかが私たちの課題なのです」
同誌のレポートによれば、ガリアーノはメゾンを引き継ぎ、最初に披露するコレクションのために「服飾史の勉強に没頭した」と語ったという。19世紀風クリノリン、20世紀初頭のベルエポック、20年代のポール・ポワレ、30-40年代のスーツ。スモーキング・スタイルに、オリエンタルなドレス。モードの歴史を重んじた50のドレスやソワレを、50人のモデルが一体ずつ身に纏っていた。900名の観客のひとりであった田口さんは、回想を続けた。「のちに彼が携わったブランドで目にする濃厚さや過剰さはなくて、色彩も黒以外には、ローズピンクやライムグリーンをグレイッシュなトーンに抑えた、静かで清楚な印象でした。中には、ユベール・ド・ジバンシィのミューズ、オードリー・ヘップバーンの劇中の姿を想起させるドレスやスーツもありました。おそらく彼が、後継者として真摯に向き合い重視したのは、ジバンシィというメゾンと、創始者本人の資質としてのノーブルさ(品格)、あるいはエレガンスだった。それらがガリアーノ流に解釈されて、私の目に飛び込んできた全てのドレスには、彼がこのメゾンの根底をなすものに深い敬意を払っていることがうかがえた。彼の才覚で“新しい時代のもの”にしていることも明らかでした。オートクチュールの真の価値を、次代に向けて牽引して見せたといってもよいかもしれません」
すべてのモデルが、「ガリアーノの作り出した服に、陶酔するように同化」していて、全員がこの舞台には一人も欠かせない“美の表現者”に見えたという。「そして同時に、ドレスとステージで、観客を酔わせていた。クチュールメゾンだけが生み出すことが許される非凡なクリエイションの訴求力と、演劇性を高めた総合演出によるショーに邂逅し、私はガリアーノを、この人は創作し続ける宿命をもつ天才クレアトゥールだと確信したのです」
田口淑子 Toshiko Taguchi
1949年生まれ。『MRハイファッション』と『ハイファッション』の編集長を務め、現在はフリーランスのエディター。
Text_ TATSUYA YAMAGUCHI