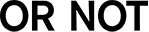TALKING ABOUT ARCHIVES Vol.08
小木POGGY基史×OR NOT増汐「古着がサステナブルでクール」日本に根づくか
リサイクル素材を使って服を作ることも大事だが、すでにあるものを長く使ったり、世代を超えて着継ぐということは、究極のサステナビリティだ。日本は、昔から古着文化はあるものの、おばあちゃんのお下がりやヴィンテージがおしゃれだという文化が根づくヨーロッパと比べて、まだ一般的にはその社会的地位が低いようにも感じる。サステナブル特集の特別対談第一弾として、ファッションディレクターとして「UNITED ARROWS & SONS」のディレクター兼バイヤーも務め、国内外でファッションアイコンとしても著名な小木“POGGY”基史さんと、二次流通にブランディングという新たな価値観を持ち込んだ『OR NOT(オアノット)』を運営する株式会社LOOPの増汐義信さんに、日本における古着カルチャーとサステナビリティについて話を聞いた。

世界ではヴィンテージ=クールがスタンダード
---本日はよろしくお願いします。小木さんは、増汐さん率いるLOOPが運営する『OR NOT(オアノット)』(デザイナーズブランドのアーカイブアイテムを中心としたECプラットフォーム)のメディアでも登場されていますね。ファッション業界の第一線で活躍される小木さんにとって、「OR NOT」はどう映っていますか?
小木:日本だと、特にデザイナーズは昔からセカンドハンド文化があるじゃないですか。ただ、古着を買うのはお金がない人で、ちょっと恥ずかしいというイメージがまだ強いと思うんです。でも、海外だとセレブ向けにブランドヴィンテージをそろえてアポイント制で買ってもらっていたり、ラッパーが昔のデザイナーズを着ていたり。
---ヴィンテージがクールだと。
小木:そうそう。ただ、日本ではなかなかそれが浸透してきていない。セカンドハンドでブランディングをやっているところがほとんどないからだと思うんですよね。大手だと多分、RINKAN(リンカン)くらいじゃないでしょうか、そこを変えようとしているのは。ECサイト内でブランディングしながらデザイナーズ古着から新品までを一挙に取り扱うという発想が今までなかったので、それをやっている「OR NOT」はすごく面白いと思います。実は、海外の人たちが欲しいデザイナーズ古着って、日本には地方も合わせて山ほどあるんですよ。
---彼らは古着を着ることに抵抗がなく、むしろ古着によって楽しみの幅が広がるような感覚ですか?
小木:そうですね。僕は海外の人から教えられました。以前から海外の人は日本に来たら普通にセカンドハンドのお店に行ったりするんです。去年、お忍びでカニエ・ウエストとキム・カーダシアンが来た時にセカンドストリートに行っていて、そういう流れが面白いなと。ただ、古着とのミックスで外すっていうのは日本独特の感覚だと思いますし、僕はもっとその日本人の感覚を磨いていくべきだと思っています。
---古着も交えてファッション自体を楽しんでいるんですね。
小木:そうです。一次流通においても、これから夏だというタイミングで夏物のセールが始まるなど、決められた仕組み自体に違和感をもつ顧客もいると思うんです。

---トレンドに乗っかってどんどん消費するのが本当に良いのか、とか?
小木:そうですね。20代前半の若い子と話したりすると、バレンシアガのようなデザイナーズブランドの次のブランドを探しています。みんなが着ていると逆に恥ずかしいみたいな感覚があるようでして、RAGTAG(ラグタグ)やRINKANとかに行って、昔のデザイナーズ古着を買う子も多いんですよね。
新品と古着の溝はなぜ埋まらないのか
---一方で、二次流通のブランディングを意識してきた『OR NOT』としては、どんな課題感を感じていますか。
増汐:先ほど小木さんもおっしゃってましたが、二次流通ってまだまだ海外のトレンドとは逆行していて、ダサいとかお金がなくてみたいなイメージを持たれている方々が一定数いるのは事実だと思うんです。。だからこそ、洗練されたイメージにしっかり作り込み、表現することを『OR NOT』では強く意識しました。
---古着でもちゃんと格好よく見せられるように。
増汐:そうです。ECとメディアの両方の部分を持ちファッション業界の方々にアーカイブの魅力を語り、伝えてもらっています。ファッションはどうしても人に付く部分ってあるじゃないですか。たとえば、小木さんのようなファッションアイコンの方がアーカイブを着ているのを見て、初めて興味を持つということもあります。なのでECで商品をただ並べるだけではなく、メディアとしていろいろな方に話を聞いて発信しています。

---啓蒙に近いイメージですね。
増汐:そうですね。イメージを変えていきたい。二次流通業界では小さい企業が結構多くて、単体で業界のイメージを変えるのは難しいんですよね。そこで、私達が旗を振ろうと考えたんです。
---『OR NOT』は、二次流通の企業とブランドと、両方付き合いがあると思うんですけど、そこで感じるギャップや課題感はありますか?
増汐:ブランドの人たちはみんなアーカイブ商品やマーケットに関心があるのに、企業としては現時点では二次流通に対して距離がありますよね。
僕は、ブランドのロイヤリティーが高い人って、新作を毎シーズン買っている人だけではないと思っています。そのブランドの名作から入ってくる人もいれば、昔からずっと好きなんですって人もいる。でも、実はここの層ってあんまりちゃんと数値化して見えていないんです。我々はECで今後しっかりデータを取り、本当の意味でのロイヤリティーが高い人を示して、ブランドとの距離を近づけていくことができると思っています。
---ファッションが好きな人って、古着も差異なく同じ服として見ている印象はあるんですが、ブランドやショップからすると距離感がある。そこになぜギャップが生まれてしまうのでしょうか。
小木:でも、昔より壁はなくなっていると思います。(アーカイブを取り上げることの多い)HYPEBEAST(ハイプビースト)やHIGHSNOBIETY(ハイスノバイエティ)のようなサイトが世界的に認知度を得てきたことも理由の一つだと思います。まずは認知してもらうことがブランドにとって大切なことで、ブランド側がアーカイブを通じて認知度を高めるという方向に移ってきているんじゃないかと。
あとは最近、Vivienne Westwood(ヴィヴィアン・ウエストウッド)の映画やマルジェラの回顧展のようなものも多い。やっぱり昔のCOMME des GARCONS、YOHJI YAMAMOTOのように今でも活躍されてるデザイナーの80年代とかの古着を見ていると迫力がすごいんですよね。
---ものを見ればわかると。
小木:いろんな思いとか魅力がやっぱり詰まっています。あとは国内外の若い世代によって再燃している90年代〜00年代の日本のA BATHING APE(ア ベイシング エイプ)やNUMBER (N)INE(ナンバーナイン)、UNDERCOVER(アンダーカバー)は、今、デザイナーのヴァージル・アブローが主流にしている”音楽的な作り方”で洋服を作り始めた第一世代で、アイデアや作り方がすごく面白い。実際のものを見て学べるということは大切だと思います。
あと、お直しの技術もだいぶ進んでいます。僕も今日、トムフォードがデザイナーだった時のGUCCIのジャケットを着てきたんですが、古着屋で大きいサイズのものを見つけたんですよ。着丈と袖だけ詰めてルーズなジャケットのように着ています。

---「そういう着方もありだよね」っていう。そういう人も増えているんですか?
小木:増えていると思いますね。原宿にfenice closet(フェニーチェクローゼット)っていうお直し屋さんがあるんですけど、その店は昔のARMANIとかのいろいろな着方も提案してくれます。
---そういうところで実際にリメイクをして、ヴィンテージなんだけど自分に合った形で着ているんですね。少しずつ古着の楽しみ方が一般的になってくるのかもしれません。
日本のファッション業界にはテックの要素が足りていない
---『OR NOT』を皮切りに、今後はもっと一次流通と二次流通の融合がされていくのかなと思うのですが、そこに向けてアパレル業界としてはどういうことをしていけばいいと思いますか。
小木:自分が学んだのは日本のセレクトショップ業界なので、そこに関して言えば、2000年代の頭くらいまで路面店ビジネスが主流でした。でも、2000年代にファッションモールに出店する店が増え、ファッションに詳しくないディベロッパーに対して自分たちがやっていることを説明する必要が出てきたんです。そういった事が重なり、プレビューとかシーズン毎のテーマを決めるという動きが生まれました。
それまではもっと謎めいたもの、一部の人だけが知っている面白さがファッションだったんですが、徐々に分かりやすいものになり、ファッション本来の面白さのあり方が少しずつ変わってきていると思います。
また、日本では、サステナビリティという考え方の普及が遅いように感じます。海外だとそれが一般的になっているし、今の日本の若い人たちもサステナブルであることがクールで、そういうブランドが格好いいって思っているんです。でも、それ以上の世代の人たちははまだその感覚に気が付けていない人も多いと思うんですよね。それと、ITとの掛け合わせが決定的に足りない。
---海外の方が進んでいるわけですね。
小木:HIGHSNOBIETYの創業者であるデイビッド・フィッシャーに取材したことがあるんですけど、日本のウェブサイトはテックの要素が圧倒的に足りないと言っていました。たとえば、HIGHSNOBIETYは、インスタストーリーのスワイプアップの技術を自分たちのwebサイトで開発して導入しています。
---技術的な部分も足りていないと。
小木:はい。日本ではファッションはこうあるべきだというこだわりが強い。それはそれで大切なことだと思うんですが、例えば日本のウェブマガジンは編集者上がりの方が多く、ITみたいな新しい流れが出てきたときに「俺わかんないからよろしく」っていう人が多いというのを聞きますし。

---IT側からはどのように見えていますか?
増汐:こういうカルチャーはある意味美しいと思っていますし、大切なことだと私も思います。ただ、変わらないといけない部分は絶対ある。小木さんは珍しいくらい、変わっていかないとという意識が高い方だなと思います。日本には、海外の人たちと話をしている人がまだまだ少ないのかな。小木さんはどうして海外で評価され始めたたんですか?
小木:僕はストリートフォトグラファーがきっかけですね。2008年くらいのある日、友達に「(ストリートスナップで有名な)トミー・トンが撮ってるJAK & JIL(スナップサイト)に出てたぞ」って言われて。何でだろうと思ったら、ファッションウィークに参加していた時の自分がスナップサイトに出てたんです。そのうちそういったサイトが重要視されるようになり、デザイナーのムードボード(コレクション参考イメージ)に載るようにまでなっていったんです。それで、知らないうちに世界の人が僕を見てくれていて覚えられていった、というのが始まりだと思います。
あと、HIGHSNOBIETYやHYPEBEASTの本国の人たちと早くからコミュニケーションをとっていました。日本では“転載サイト”みたいに言われていたけど、絶対にこれから需要があると思っていて、自分達で海外にプレスリリースを送っていたんですよね。だから、これからサステナビリティを考えないと格好よくないということは、肌で感じています。

増汐:前、ダンボールの話があったじゃないですか。ネット通販がこれだけ普及すると世の中に不要な段ボールが溢れてる。商品を発送する時にダンボールの廃材をつなぎ合わせて使った方が、企業としてのメッセージや世界観が伝わるはずだと。その話を小木さんからもらって「たしかに!」と思いました。世界基準で見たらこれがクールですよと言われて。こういうのって世界を知っているからこそのアイデアだと思うんです。
若手のカルチャーをフックアップするべき
---アパレル業界の人にしても、物の売り方・買い方が変わる中で、実際悩んでいることはたくさんあると思うんですよね。うまく融合すれば、もっとファッション業界も面白くなると思うのですが。
小木:そうですね。もっと若者のカルチャーが根付いていくといいのかもしれません。(アーティストの)VERDY(ヴェルディ)くんの出現とかは僕はすごくいいことだと思っています。アメリカだと若い子たちがどんどん出てきて、ラッパーとかも次々面白い子たちが出てくるんですよ。
ヴァージル・アブローはルイヴィトンと仕事をしていても、チームでチャットグループを作って若い人たちにも「面白い事があれば連絡してくれ」と伝えているんです。彼と働いている人たちは、自分も参加できて楽しいと言っているようです。本来だったらデザイナーは、生地の展示会にいったりデザインに磨きをかけたりするのでしょうが、ヴァージルはアーティスティック・ディレクターとして世界中を旅してDJをして、若い人たちに音楽を通じてカルチャーを伝えて、面白い人がいたらすぐコラボレーションしようってピックアップして。世界中に仲間を作って、ファッションのトレンドを作っているんです。
---そういう若い人たちの文化は、日本はまだ全然できていないと思いますか?
小木:そうですね。日本だけで見ると少子化ですし、その逆をいってしまっている。だから、VERDYくんのように世界中に友達を作って発信しているのはすごく良いことだと思います。彼の登場からちょっと変わってきてる気がします。
サステナブルの本質はどこにある?
---サステナブルにはいろいろな定義があると思うのですが、小木さんとしてはどのような視点で見ていますか?
小木:以前、広島でおきた洪水被害によって多くのデニム工場が浸水したじゃないですか。デニムって汚れても格好いいんですよ。だけど、浸水した生地は大きな企業では使ってもらえなかった。そういうところから変えられることがたくさんあると思いました。
---決まりがあって、ダメなものはダメっていう。
小木:そういう考え方もあるんだなと僕はその時思いました。実は自分がアドバイザーとして関わっているお店があって、9月にサステナブルをテーマにしたお店をオープンする予定なんです。やっぱりサステナブルってなるとヨガとかほっこり系にいきすぎちゃうお店が多いと思うんですけど、そことファッションをミックスしたお店になります。
---それはかなり面白そうな取り組みですね。二次流通ビジネスに携わる増汐さんは、サステナブルをどういう定義で捉えていますか。
増汐:定義っていうのは難しいですよね。でも、一枚の服を中心に考えた時、私が着て不要になったとしても世界の誰かは必要としている。そういう人に言語やシステムの壁も乗り越えて当たり前に届けることが出来る。そういう仕組みを作っていくのが私達の役目だと思っています。

---一年2回のシーズンに合わせて作る業界のサイクルをどのように見ていますか?
小木:それはそれで続いてほしいという思いはあるんですが、これがかっこいいという考えを消費者に押し付けてしまっている部分もあると思うんです。消費者に楽しんでもらうやり方はシーズン毎に何かをやるだけじゃなくて、別の方法もあるのかなと。
---それは消費者と直接コミュニケーションを取るしかないですか?
小木:そうですね。海外の方はそういうのを敏感にクイックにやっているような気がします。
---日本と海外で、何が違うんでしょうか。
小木:海外はカルチャーに投資してくれる人は多いですよね。日本だとそれをやることによってどれだけの効果が生まれるのか、みたいな話が先にきちゃうので。じゃあ次のシーズンに考えよっかみたいなパターンで終わっちゃうことが結構多い気がするんです。海外の方が「やっちゃおうぜ!」みたいな感じ。
日本ファッション市場の可能性を拡げるには
---これから洋服の価値を消費者に伝えていくには、どういう接し方や伝え方をすればいいと思いますか?
小木:お店はちゃんとメッセージを発信する場であるべきだと思います。メッセージ性の強い服か思いっきりシンプルで上質な服。AURALEE(オーラリー)のような服を支持する、ちゃんとした目を持つ消費者が日本にはすごく多いんですよ。逆にsacai(サカイ)のようなデザインとメッセージ性が共存する服の付加価値にも共感できて、シンプルで上質なものも受け入れられる。そこが日本のいいところでもあると思うんです。
あとは、海外の人も参加できるのがいいですよね。日本のシステムは海外の人が入りにくいことが多いみたいです。例えば、好きなブランドの会員登録をしたいけど日本の住所がないとできないとか。そこは絶対に改善すべきです。
日本ほどファッションの店がひしめきあっている国はないなと思うんです。そういう良さをもっと世界の人に一緒に参加してもらえるように、ITの方達の力を借りてシステムから変えたい。やっぱりファッションの人たちの頭だけ考えてると限界があると思うんですよね(笑)

増汐:でもIT側からは、ファッション側の人たちがこういうこと考えてるってあんまり分からないじゃないですか。業界的な距離感がものすごくある。小木さんの話を聞くと、できることはたくさんあるんじゃないかと思いました。
小木:海外の人たちは、90年代に裏原宿カルチャーから発信されたファッションに不動産的な価値観を持ち込むやり方を新しい形で広めているんですよね。古い物に新しい価値を吹き込んでその価値を高めた。それを今、ヴァージルや(ディオール・オム アーティスティック・ディレクターの)キム・ジョーンズが世界的に発信していて。本当はRAGTAGとかRINKANがやっていたことだったり、Laila Vintageのブランディングだったりと日本が早かったんですけど、今はアメリカの方がそういうのをビジネスにしてる人が多いと思います。
日本で見れば、LAのRound TwoのSean Wotherspoonのようにセカンドハンドの中からカリスマみたいな人がまだ出てきていないし、アメリカは偽物が多いので、日本の鋭い審美眼がもっと評価されていくと良いのかなと思います。それに、海外ではブランド割り振りがざっくりですが、日本は細かくコレクションの分類までされている。そこも日本の良さの一つだと思いますね。

---たしかに。お二人の話から、二次流通も含めた日本のファッション市場のポテンシャルを感じました。テクノロジーをうまく利用したり、サステナブルがクールだという若い世代のカルチャーをフックアップするのが鍵になりそうですね。ありがとうございました。
小木“POGGY”基史
1976年生まれ。1997年に「UNITED ARROWS」でアルバイトを始め、プレス職を経て2006年に「Liquor,woman&tears」をオープン。2010年には「UNITED ARROWS & SONS」を立ち上げ、ディレクションを手がけている。2018年に独立し、昨年リニューアルオープンした渋谷PARCO内の「2G」のファッションディレクターを務めるなど、新たな動きにも注目が集まっている。

Weare
テクノロジーとイマジネーションで「ひと」と「衣服」の
新しい未来をつくるコミュニティプラットフォーム
https://weare.sitateru.com/
Text_ SHIORI OGAWARA, TAKAHIRO SUMITA