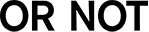GUCCI 2019 S/S COLLECTION
カルト映画から生まれる GUCCIの倒錯した世界
「恐怖」、「絶望」、「倒錯」、そして「暴力」。それらの要素は、デザイナーにとってインスピレーションを求めやすいものなのかもしれない。その証拠に、これまで数多くのデザイナーが、ダリオ・アルジェントやロマン・ポランスキー、アルフレッド・ヒッチコックらのホラー/カルト映画をコレクションのテーマに掲げてきた。今は亡きアレキサンダー・マックイーンを始め、ニコラ・ジェスキエール、ラフ・シモンズ、高橋盾と、カルト映画マニアのデザイナーを挙げるとキリがないぐらいだ。ただ、現在のファッション業界において、誰が一番そのカルト的世界をクリエイションに反映しているかと問われたら、迷わずGUCCIのアレッサンドロ・ミケーレと答えたい。彼のホラー/カルト好きは、はっきり言って度が過ぎている。ブランド史上初となるパリでの開催となった2019S/Sのコレクションでは、オープニングでいきなり1960年代から80年代にかけて活動したイタリア・アバンギャルドの鬼才、レオ・デ・ベラルディニスと、パオラ・ペラガッロによる映画『A Charlie Parker』(1970)を上映し、観客の度肝を抜いた。そのおどろおどろしい意味深な映像は観る者の胸をざわつかせたが、この作品とそれを手がけたレオとパオラの存在こそが、今シーズンのGUCCIのテーマであるとともに、「妄想に取り憑かれ、野蛮で、分裂した(断片的な)プロット」というミケーレのコンセプトの出発点であった。レオとパオラが催したアングラ劇場さながらの会場では、レトロかつフェティッシュな服に身を包んだモデルが次々と登場していたが、中にはスタンリー・キューブリックの『時計じかけのオレンジ』(1971)からの引用だと思われる要素も見ることができた。
レオとパオラやキューブリックなど、カルト的要素を取り入れたミケーレのクリエイションは、何も今シーズンだけの話ではない。2018A/Wコレクションでは切り落とされた自らの頭部を手に抱えたモデルたちを登場させ、2019年クルーズでは南仏アルルの墓地(古墳)をコレクションの舞台に選び、さらに2018プレフォールに出版された『Disturbia』では、アルジェントの『インフェルノ』(1980)や『シャドー』(1982)からインスピレーションを受けて作られていた。
ホラーやカルト映画のマニアック世界観を、GUCCIという世界規模のブランドを通して表現する鬼才ミケーレ。彼のフェティッシュなアウトプットは今後も加速していきそうだ。次のコレクションはどんな映画をモチーフに、どんなコレクションを発表するのだろう?想像しただけでも胸がいっぱいになる。
Text_ SOHEI OSHIRO