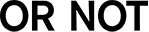INTERVIEW WITH CHIKASHI SUZUKI
写真家鈴木親が語るファッションの変遷_2010年~2020年代編
2010年代からSNSが日常生活の一部に組み込まれていきました。親さんはこのコロナ禍の中でインスタグラムを始められましたね。どのようなきっかけだったのでしょうか。
非常時に何か新しいことをするというのが自分の中の習慣です。この間に自分で動画を編集できるようになりましたし、今まで一切まともにやっていなかったPHOTOSHOPも少しずつ覚え始めました。写真を切り抜いたり明るくしたりもできるようになりました(笑)。
更新していく上で考えていることはありますか?
丁度、三千人くらいで止まるようにしています(笑)。それくらいがちょうどいいですね。例えば雑誌でも、これは90年代の数字ですが、十万部以上売れると、自分たちとは異なる作法の人たちも見始めるので、規制がどんどん増えていきます。なので、一万部から三万部くらいの間が一番自由ですね。でも、インスタグラムだと一万人のフォロワーだと少し多すぎるようにも感じます。雑誌は毎日見るものではないと思いますが、インスタグラムは違いますからね。

今ではブランド、メディア、消費者のいずれもが同一のフォーマットで双方向的にイメージ共有をしていますね。
プロが作り込んだヴィジュアルより、素人が突発的に作ったイメージの方により多くの「いいね」が付くこともありますね。でも、パッと見では分からないものに対しての幻想や憧れも大切です。玄人に対しても響くイメージと、一般の人にも届くようなイメージの両方をおさえていなければ、これからのブランドは成立しないと思います。それは同じものではなく、違うものを別々にやっていく必要がありますね。
ブランド側がファッションエディターと手を組み、オリジナルコンテンツを制作していく流れがありますね。ある意味、雑誌的な発想でブランドのコンテンツを作り始めています。
その流れを最初に作ったのはGUCCIですね。『DAZED&CONFUSED』のアート・ディレクターをしていたクリストファー・シモンズが入ったことによって今の流れができました。SNSは、毎日見るものなので飽きさせないようなコンテンツが大量に必要になってきた、という社会背景もあります。彼らによって、昔のように一つのイメージをいっぺんに見せるというスタイルではなく、様々な視点から成るコンテンツをキュレーションするという方法が確立されました。あらゆる層を網羅しつつ、全体の世界観をキープするようなやり方です。
ブランドと写真家の関係も変化していますね。一人の写真家が一つのブランドのイメージのみを継続的に撮り続けている、というケースも減ってきていると感じます。
例えば、90年代頃の写真家グレン・ルッチフォードがブランドを撮る時などは、契約したブランド以外を撮影してはいけないというルールがありました。色々なブランドを撮っていると広告の信用を保てないと考えられていた時代でした。でもそんな時、グレンと仕事をしたいと思った『DUNE』の林文浩さんと編集者のアンドリュー・リチャードソンが手を組んで作ったのが『RICHARDSON MAGAZINE』。「服を着ていないモデルを撮るのであれば問題ないだろう」という発想です(笑)。その頃は、カメラマンにもモデルにもそういう固い縛りが付いていました。でもその分、契約金は跳ね上がる。なので、広告のキャンペーンが一つでも入れば、その間は他に仕事をしなくても成立していました。ただその後は、どんどんメディアが増えて行くに連れて、様々な種類の広告を作る必要が出てきました。そうなると莫大な予算が必要になるので、2000年頃を目処にそういった契約が少なくなっていきました。今は一人の写真家が同じシーズンに違うブランドの広告を撮るのは当たり前ですよね。また、インフルエンサーの子たちも色んなショーに行くようにもなりました。少し前までの囲い込むような流れから、ブランド同士でシェアしているようにも見えます。そういった時代にブランドの特色をどこで出すのかと考え始めたことをきっかけに、ロゴや分かりやすく目立つようなデザイン方法が席巻してきたのだと思います。

一方で、ここ最近の傾向としては、リアルへの希求も如実に現れていると感じます。特に今期は、物質性を意識したインヴィテーションを作るブランドも多かった印象です。
例えばLOUIS VUITTONがそうですよね。世界中の人が同時配信で観られるようになりましたが、ショーに招待されるゲストには未だにインヴィテーションが届きます。ひと昔前は、ただの封筒でしたが、今ではギフトボックスのようなしつらえで物質感があるものが好まれる傾向になっていますね。でも、実際に会場で使うのはデジタルインヴィテーション。写真の流れと同じで、一番マスに対して響く仕掛けと、玄人の層にも響くような仕掛けを使い分けるブランドが増えているように感じます。
ここ最近のファッションにおける映像表現の中で気になる動画はありましたか?
この機会でないと見られないような部分を見せてくれたという意味では、ジョン・ガリアーノが手掛けるMAISON MARGIELAのドキュメンタリー映像『S.W.A.L.K.』は凄いと思いました。普通、オートクチュールの舞台裏は見せてもらえませんからね。縫子さんの作業なんて絶対に見学できない。そこに映っている世界がフィクションだとしても、その行程をやっているという事実がありますからね。
今この時代に生まれた衣服がその後、新しい価値を帯びるにはどのような行程が必要になるのでしょうか?
街中のスナップ写真もそうですが、今日撮った写真を明日見せても人は感動しませんよね。でも、例えば20年後になると街や風景は変わっているので、その写真もまた違って見えてきます。当たり前ですが、今はもう撮れないという点に価値がある。そしてその価値は、時代を経ても依然としてイメージが残っていることから生まれているのだと思います。なので、マルタン・マルジェラが引退した今でも、形を変えながら継続しているという部分に価値がありますし、ヘルムート・ラングに関しても、彼のフィロソフィーを沢山のデザイナーたちが受け継いでいるからこそ新しい価値が出てきたんだと思います。

一つのブランドの歴史の中でも写真家の起用がキーになっていますね。今お話にあがったマルタン・マルジェラとジョン・ガリアーノの写真表現に対する考え方の違いも現代を考察する上では示唆的だと思います。
これは主観ですが、マルジェラは立派なものに見えないようにわざと素人っぽい写真を選んでいました。その選択が結果的にマルジェラを特別な存在に押し上げたのだと思います。逆にジョン・ガリアーノは、ニック・ナイトを起用していることからも分かるように、立派そうに見える写真も好きですよね。でも、その中で新しい映像表現だったり自分らしさを探求しています。そのトライアルし続けている姿勢がかつてのマルジェラに近いと思います。それにブランドへのリスペクトが入った上で自分らしさがあるので、誰かのオマージュをやり続けている人たちよりも断然好きですね。彼は確実に新しいマルジェラ像を作ったと感じます。
マルタン・マルジェラとジョン・ガリアーノは、オートクチュールへの造詣の深さという点でも共通しますね。
昔、マルジェラは『PURPLE』にオートクチュールの服を解体し、型紙やステッチが解れてる写真など、制作プロセスを掲載していたことがありました。それは、オートクチュールに関わる人たちに対するリスペクトから生まれた表現です。ジョン・ガリアーノもオートクチュールをよく理解している人なので、共鳴しているところが多くあるんだと思います。しかし、いわゆるハイプな服には、そのフィロソフィーはないですよね。結局のところ、そういった服の作り手たちは出来上がった後のことが中心のデザインです。
現代の現象を多様化が進んでいると総括する向きもありますが、実際そこで起きているのは、ある意味プロレス的とも言えるような新鮮なアングル設定と分脈読みのゲームのような気もします。
ヴァージル・アブローのような仕方でファッションの世界を更に広げている人もいます。それも一つの役回りだとは思います。昔でいうと、GIORGIO ARMANIが新しいシルエットをドーンと発表した後、一気に他のデザイナーが真似するという流れがありました。でも今は、その流れが色んな方向に細分化されているように感じますね。
今は、消費の仕方も細分化されていますね。メディアやプラットフォームにはコンテンツが溢れていて、そこから好きなものを好きな時に取り出せるような時代です。また、遥か昔のコンテンツを今日のものとして見ている傾向があるように感じています。動画を観ている時も、普通は公開日を気にすることはないですよね。
確かにそうですね。色んな人の価値観と時間軸が入り込んで滅茶苦茶になっているのかもしれません。もう一つ危ないのは、スマホに流れているイメージが全て自分の素材だと思ってしまうということ。そこにあるからこれを使えばいいみたいな感覚とでもいいますか……。しかも今はカメラもPCも性能が良いので、技術的には何でもできてしまうが故に、自分が何でもできると思ってしまう。そういう積み重ねは、彼らの後のクリエーションにも響いてくると思います。ですのでまず、自分の時間軸を作ることが必要だと思います。
かつてのデザイナーは、自身の生き方や生活様式、趣味嗜好から生み出される服作りで、音楽でいうところのロックスターのような存在だったと思います。今は、どちらかというと時代に求められている衣服を適切なタイミングとシチュエーションで提供するというDJ的な発想に近いと思います。
サンプリングは、イメージを効率的に広げる為の方法論だと思います。しかし、ファッションにも写真にも完成までの途中過程が良かったということがありますよね。ゼロから作る人は、その中間に美を見い出すことができます。一方で真似をする人たちは、基本的に何か既存のものに近づけていく作業なので、その許容範囲が狭い。もう一つ写真の例でいうと、無名のカメラマンでも有名な人を撮った写真はみんなに見てもらうことができる。でもその有名人が持つ価値が自分の価値だと錯覚してしまったら、その人にはそれ以上の成長はないですよね。

新しいものに対する評価の仕方も時代と共に移り変わっていますね。かつては、デザイナー同士のデザイン的な実践が一つの評価軸でしたが、今では統計的に数値化できるものの評価がスタンダードになっているように感じます。
例えば、10万円の衣服を20万円の価値に見せるのが主流だった時代に、マルジェラは10万円の服を1万円に見せるようなデザインをしました。それでもみんなが買ったのは、彼のフィロソフィーを身に纏いたいと思ったからです。作り手側の人間は、そういった新しい価値を作っている人を尊重し応援すべきだと思います。僕らみたいなものまでが、ハイプなデザインを評価してしまったら誰も新しいもモノ作りをやらなくなってしまいます。二番手の方が得だと思い込んでしまいますので。そこは意識的にしています。たまに欲しいスニーカーもありますが(笑)。
技術的には、様々なイメージが簡単にコピーできるようになりました。コピーできないものがあるとしたらどのようなものでしょうか。
つい先日出版した『新東京』は、20年分のわざと下手なスナップ写真だけを選んだ写真集なのですが、例えばその中に樹木希林さんのお孫さんのUTAくんが赤ちゃんから大人になるまでの記録が入っています。いくら僕の手法をコピーする人がいたとしても20年前の写真は撮れないですよね(笑)。あとは、ある雑誌の企画で篠山紀信さんがウォルフガング・ティルマンスを撮影している最中を撮った写真も入っています。もちろん、篠山さんが撮ったティルマンス単体の写真も貴重ですが、今見ると篠山さんが大判カメラでティルマンスを撮ってるという光景もまた貴重ですよね。そんな瞬間は、中々演出できるものではないので、時間が経てば経つほど面白く見えてきます。日常の何げない風景が写り込んだ写真は、構えて撮った写真とはまた違った価値が生まれてくるのだと思います。
雑誌のエディトリアルページでは、ご自身もキャスティングに参加される時があるかと思いますが、どのような基準で選んでいるのでしょうか。
パッと見はボサっとして見えるけど、服を着せた瞬間にイメージがガラッと変わるような人が好きですね。撮影中にポージングをあえて指示しないのも、困っている所作をしている時が一番ちょうどよく写るからです。例えば「色気を出して」という指示を出してしまったら嘘っぽくなりますし、曖昧な表情をしている時の方が色気があるように感じます。そもそも、撮影は本人の出したいイメージが出る前に終わらせています。その人が望むその人になる前に撮り終えてしまえば、演じていない自然な表情が撮れますからね。

最後に親さんの撮影方法に関してお尋ねしたいと思います。以前、スタジオ撮影ではHMIのライトで撮影されていると聞きました。これは、荒木経惟さんも使用しているライティング機材になりますね。
写真らしい表現とは一体何かと考えた末に、フィルムの手ブレが大切だと気付きました。例えば、IPHONEにもわざわざフィルム写真っぽく見えるような加工機能がありますよね。それは、まだ多くの人にとって「写真=フィルム」というイメージがあるわけです。また技術的な事を言うと、ストロボであれば1/125秒のシャッタースピードなので視覚的に追うことはできませんが、HMIは1/4秒とか1/35秒なので、人間が視覚的にも感じられるその瞬間が一枚の写真に封じ込められていることになります。広告的にピタッと止まっている立派な写真が多い時代には、その手ブレ感がよりポエティックに感じられるのだと思います。
親さんは、先人たちの生きた方法論を探り、コレクションすることを通じて自らの眼差しを更新し続けている印象があります。先行世代が培ってきた技術を用いる際にも、ご自身にしか撮れない写真を撮るためにどのようなことを考えていますか?
先ほどのHMIは、ストロボが開発される前のライティングでブルース・ウェーバーなど大御所の写真家も使っています。なので、もちろん荒木さんだけではなく、そういった写真家たちの歴史も踏まえています。しかし、その上であえて自分の特徴を言うのであれば、被写体に一切触らないという点が大きいと思います。これは、スタイリストの北村道子さんに言われて気付いたことでした。僕が撮りたいのは、小津安二郎の世界観という訳ではないのですが、白いブラウスの二の腕あたりの袖からブラジャーが透けて見えるような一瞬です。荒木さんは「アラーキー」としてモデルに向かって真正面からぶつかり色気を最大限に引き出す方法を発明しましたが、僕は抑制された中にある色気を追求したいと思っています(笑)。
Interview text_ SHINGO ISOYAMA