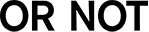INTERVIEW WITH CHIKASHI SUZUKI
写真家鈴木親が語るファッションの変遷_2000年~2010年代編
2000年代から2010年にかけての大きな変化というと、2004年に『PURPLE』の編集者エレン・フライスとオリヴィエ・ザームがそれぞれ別の道を歩みはじめました。そして2008年にはマルタン・マルジェラが自身のブランドを引退されています。
そこがファッションの境目ですね。以降はいわゆるハイプなものが席巻していきました。単純な言い方をしてしまうとセレブリティありきのファッションで、その流れが今現在にも続いていると思います。マルジェラが脚光を浴びていた頃までは服が強ければ誰が着ていても良い、という価値観でした。当時のエレンは、自分の近くにいる人たちをモデルとして起用し、コンテンツを作るという発想だったので、どんどんズレが大きくなっていったのだと思います。

その境目において、エポックメイキングなファッションフォトグラフィーの表現はありましたか?
その頃のユルゲン・テラーが、ファッションフォトグラフィーにおけるスナップ表現を次のフェーズに押し進めました。例えば、35mmのカメラで普通に撮影すると当時主流の中判、大判カメラと比較して服のディテールが潰れてしまうのですが、彼は日中シンクロといって明るい屋外でストロボを発光させることで暗い部分を明るく写しました。しかも、クリップオンのライトを顔に当てるとシワを飛ばせるのでレタッチいらずという(笑)。ある意味コロンブスの卵のような発想ですね。実際その後、テラーの影響で多くの人が同じような撮り方をし始めました。手法は、簡単なほど流行る傾向がありますしね。
時代と共にファッションデザイナーという仕事の役割も少しずつ変化していきました。例えばトム・フォードは、1994年にGUCCI、2001年にYVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHEの「クリエイティヴ・ディレクター」に就任しました。
トム・フォードはファッションの世界でのクリエイティヴ・ディレクターとして最初期の人だと思います。歴史あるブランドをリニューアルするという方法論を確立した人ですね。彼は、ライセンス事業等でバラバラになっていたブランドのイメージを整理することからはじめて、徐々にトータルイメージをコントロールしていきました。彼が編み出した作法が今のハイブランドにおけるデザイナーの在り方を作ったのだと思います。
トム・フォードとは、また違う仕方で当時のシーンの在り方を一新させたデザイナーとしてエディ・スリマンの名前が挙げられますね。
実は、DIOR HOMMEの初ショーのバックステージに僕と『SELF SERVICE』のチームで入ったことがあります。今でも忘れらないのが、カメラを構えてモデルに着せつけているエディを撮ろうと思った時です。彼がいる背景は画的には少し地味でした。でも僕たちとしては、どんな状況でも撮らなくてはいけない。その瞬間、彼は何か撮っているなと恐らく気付いたんです。そのコレクションは、赤がキーカラーだったのですが、彼は赤いバックボードの前にサッと移動して、またモデルに着せ付け始めました。自分がどう写るのかという画が本当に良く見えている人で、他のデザイナーと全く毛色が違う人物が現れたなと思いました。普通のデザイナーであればショーの直前はかなりナーバスになっていると思うのですが。
2008年には、フィービー・ファイロがCELINEのクリエイティヴ・ディレクターに抜擢されましたね。彼女もまた当時毛色が異なるデザイナーだったと思います。
今までの女性のファッションデザイナーは、ワーキングハードなイメージが中心だったと思います。言ってしまえば、仕事に没頭しているようなイメージですね。しかし、CELINE時代のフィービー・ファイロは自ら育児休暇を導入しました。また、オフィスもパリの本社ではなくロンドンのオフィスに拠点を移しましたね。これはもう僕の主観ですが、その当時のファッションは凄くフランス的なデザインが席巻していたように感じます。その流れをイギリス的な方向に切り替えたのがフィービーでした。例えば、彼女がデザインする鞄のディテールなどはイギリスの手帳メーカーSMYTHSONに近いですしね。またイギリス人は、スーツの内側に芯を仕込んでまっすぐシワにならない硬い生地を好む傾向があります。イタリアなどの着やすくて柔らかいスーツがいいという価値観とは対照的です。そんなイギリス的な美意識を基軸に女性的な柔らかさを表現するため、ボンディングの生地を使い始めたのだ思います。僕たち撮る側にとっては、撮影においてシワを入れるか入れないかは大きい要素なので、コレクションに関してもそのような目で見てしまいますね(笑)。

生地に対する感覚に国柄が出るというのは重要なご指摘ですね。
例えば、日本ではより硬くてユニフォーム的な生地が好まれる傾向があると思います。あるいはスニーカーに関しても、アメリカではADIDASのスタンスミスやスーパースターなども柔らかくなってシボ感のある革の状態が高級とされますが、逆に日本ではピンと張った状態の靴が高級品とされますね。
2000年代は、雑誌媒体がモードファッションを浸透させる大きな要因だったと思います。日本においては、どのような広がり方だったのでしょうか。
やはり、日本でモードブランドが受け入れられてきっかけとなったのは、スタイリストの祐真朋樹さんと野口強さんの功績が凄く大きかったですね。特に彼らが作った『BRUTUS』と『ミスター・ハイファッション』のエディトリアルページが大きい。例えば二人がDIOR HOMMEのページを作る時、もちろん外国人のモデルのページも作っていましたが、二人がその服を着ているページが続き、その後に20~30着分の物撮りの見開きが来るような構成です。ヨーロッパの雑誌ではスタイリストの私服が掲載されることはあまりないですし、ましてそこに物撮りが来ることもありませんでした。
当時でいうと、POETRY OF SEXの千葉さんもまた、現代に繋がるファッションの感覚をお持ちの方だったと思います。
千葉さんに関しては、本当に面白い話がいっぱいありますよ。リチャード・プリンスをホテルで出待ちして、現金200ドルを渡して「Tシャツを作ってくれ」なんて言い出すような人ですからね(笑)。でもそれで、本当に『THE HIPPIE DRAWINGS』の絵を使ったTシャツを作ってしまうのが千葉さんの凄いところです。大物の人ほど「コイツなんか、ヤバイな」と思ったらOKしてくれますからね(笑)。それもMARNIがリチャード・プリンスとコラボレーションするよりもずっと前の話です。彼は、自分の中の美意識がすごくあって、それを無理やり通すから毎回揉めるし、彼を嫌っている人が多かったのも事実です。でも彼の中では『PURPLE』とか『DUNE』とはまた異なる世界観をTシャツで表現しようとしていました。実は、僕がスタイリストの北村道子さんに初めてお会いしたのは、千葉さんにTシャツの撮影を頼まれたのがきっかけです。確かリチャード・プリンスやエレン・フライス、レティシア・ベナの絵を使ったTシャツを北村さんに着てもらうという企画でした。当時はアートTシャツみたいなものはありませんでしたし、今でいうところのUTの原型にもなっていると思います。

その後、多くのブランドがアートTシャツを手がけるようになってきましたね。
一気に火が付いたのはMARC JACOBSが村上隆さんとコラボレーションしたタイミングですね。でも僕にとって衝撃的だったのは、アーティストとのコラボが流行りだしたタイミングでBALENCIAGAのニコラ・ジェスキエールがクリスチャン・ラッセンのTシャツをアートTシャツとして販売したことです。皮肉が効いていてカッコいい(笑)。
確かにニコラ・ジェスキエールは、シーン全体を俯瞰して最適な一手を刺すような姿勢が垣間見えます。『PURPLE』との繋がりでいうと、編集部と親交の深かったドミニク・ゴンザレス=フォルステルがBALENCIAGAの店舗ディスプレイや香水のデザインをしていますね。
そこで大切なのは、ニコラがBALENCIAGAに入った時に、MARTIN MARGIELAにいたアクセル・ケラーがコミュニケーション・ディレクターに就いたという点です。恐らく彼が『PURPLE』と近かったのでドミニクとコンタクトを取ったのかもしれませんね。最初のBALENCIAGAのコレクションは、確か、『VOGUE』と『PURPLE』にしか撮影サンプルを貸していませんでした。絞ることによってブランド全体の方向性を定めていったんだと思います。その結果、ニコラの存在をもの凄く高みに持って行ってくれました。今、アクセルはJIL SANDERの社長です。いわゆるメガブランドではないブランドにも関わらず、シーンに存在感を残しているのは、もちろんデザイナーのルーシー&ルーク・メイヤー夫妻のクリエーションがすごく優秀なのは大前提ですが、コミュニケーションの部分をアクセルが担っているというのも大きいと思います。当たり前ですが、ファッションのキープレイヤーはデザイナーだけではないですからね。
現代のファッションにおいてもキープレイヤーは業界の内外に点在していると思います。先ほど、村上隆さんのお名前が上がりましたが、親さんは2000年に渋谷PARCOで開催された村上さんキュレーションの展覧会『SUPERFLAT』にも参加されていますね。
雑誌『BRUTUS』の連載企画の写真を見た村上さんから連絡が来たのがきっかけです。今の『BRUTUS』の少しダジャレっぽいページに繋がるようなニュアンスで、全て望遠レンズを使って撮っていました。その時、村上さんに言われたのは「何故、君はガードレールを入れて撮っているの? 日本の写真家は、みんな避けているよね」ということ。ガードレールは、ヨーロッパでは中々見ることがないので、意図的に入れておくと海外の人から見るとかなりグラフィカルで、東京らしく写ります。自分にとっても、そこにあるものでいかに東京らしさを表現するかが大切なので。ですが、当時の日本の写真家たちは、いかにヨーロッパ的に見えるかばかりを考えていたように感じます。フランス風の建物が都内に建設された時などは、みんなこぞってそこに撮影しに行ったりしていました。そんな写真を見ても外国の人たちは何も感じませんよね。でも僕も、そこに気付けたのはエレンの言葉が大きかった。海外でちょうど一年を過ごした頃、エレンに「作品は撮れたの?」と聞かれました。「一つも撮れていない」と返すと、「それは正解だと思う。一年しかいない人が本当のフランスを撮れる訳が無い。そんな風に答えてくれたあなたを信用する」と言ってくれました。それを聞いて、すぐ帰国した方がいいなって思いましたし、それが今の自分の作家性に繋がっていると感じます。

親さんは、中野ブロードウェイ周辺をよく撮影スポットに選ばれていますね。中野には、村上隆さんのギャラリー「HIDARI ZINGARO」もあります。ですが、日本に戻られてからしばらくは「都市と人を写す」という視点での撮り方はされていなかったと思います。
当時は、街で撮った写真に日本語が写った看板があると、全部消せと言われていました。今みたいにレタッチで気軽に修正できる時代ではないので、工事現場の後ろにあるただの白い壁を撮って、これなら文句はないだろうと思っていましたね。その一方で、海外の雑誌では、今にも繋がる撮り方をトライしていました。80年代は、仲條正義さんの元、篠山紀信さんが『花椿』の誌面で、COMME DES GARÇONSを日本家屋の中で撮るといった写真がありましたが、その後がいわゆる白人モデルを起用する流れがきました。その約十年間の時間は、自分にとっては空白の期間です。でも『PURPLE』で撮り続けるうちに日本でも仕事が来るようになり、懲りずに撮り続けていくうちにそれが段々とスタンダードになっていきました。中野を撮り始めたのは、新宿と秋葉原の間みたいで面白いかなと思ったからです。新宿というと荒木さんのイメージがありますしね。中野は、細い路地に電線が横切っているのにも関わらず空が近く感じます。それに、小さな風俗街や飲み屋があったり、中野ブロードウェイがあることでいわゆるオタクの人たちもいます。もの凄い日本的な空間だと思ったのがきっかけです。
その頃の親さんの写真をまとめて見ることができるのが写真集『SHAPES OF BLOOMING』ですね。POETRY OF SEXの千葉さんが主宰するTREESARESOSPECIALから2005年に出版されています。こちらも、発売されるまでに約一年間くらいの時間が経っていると聞きました。
その頃、全部の本にISBNコードを入れるという流れがありました。そんな中、例の千葉さんが「そんなコードなんて入れなくてもいい」という風に言ってくれたので作ろうと思いました(笑)。でも最初に出版する本なので、アレも入れたいコレも入れたいと色々考えすぎてしまい、結局一年くらい放置していました。その後、ウォルフガング・ティルマンスが『I-D』で撮っていた方法論にも近いのですが、ファッションとポートレートが混ざりあったような本にしようと考えました。ある人から見るとファッションの写真集に見えるし、また別の人から見るとただのポートレート集に見えるという構成です。例えばモデルの私服スナップがファッションフォトグラフィーに見えたりする瞬間がありますよね。ランウェイにあるものだけがファッションの全てではないですから。

それは同時代的な価値観も関係するのでしょうか。例えばその頃、アン・ソフィー・バックは、私服のままのモデルをランウェイにそのまま出していましたよね。
正にそうですね。意図的にやっていた部分もあります。この本には、ANN-SOFIE BACKの服やBERNADETTE CORPORATIONの服も入っています。そして、私服をまとったヴィト・アコンチやソフィ・カル、トゥイー・ファムも撮りました。そういう意味も含めて、後から見るとその時には気付かなかった、その時代特有の空気感が流れているのかもしれませんね。
これまでに様々な国籍の方々を撮影されてきたと思いますが、国ごとの光の違いはどのように感じていましたか?
まず、湿気があるかないかというのが凄く大切です。そこで、カラッとしたイメージになるかならないかが決まります。それと、当たり前ですが日照時間が各都市によってかなり異なります。ロンドンは、横から来る光がすごく長く続きます。昔の『I-D』を見るとわかりやすいのですが、横の光を上手く使って立体感があるイメージを作っていますね。一方、東京は横から射す光の時間が短いですね。

例えば、日本人が意図的にヨーロッパのパロディーを行った時に生じる違和感のようなものにも、価値が生じることはありますか?
『VOGUE PARIS』で撮っていた七種諭さんは、その例に当てはまるかもしれませんね。彼が評価されたのは『VOGUE ITALIA』の誌面で、日本の雑誌『OLIVE』のような世界観で撮影をしたことがきっかけです。ある種、西洋のパロディーなのですが、一周回って面白いという評価になりました。そこでも大切なのは、日本的なものをいかに客観的に見せるかという視点です。洋服自体も西洋から生まれたものなので、やはりヨーロッパの基準を理解しなければ見てすらもらえないと思います。
その基準を理解した上で、いかに日本的な文脈を入れ込んでいくかが親さんの作家性にも繋がってきますね。そこで大切なのは、嘘と本当の織り交ぜ方についてだと以前から話されていますね。
どのジャンルでもそうですが、その織り交ぜ方が作品を作る上では一番重要だと思います。例えば、今日のインタビューもそうですよね。実際、僕が喋っていることなんですけど、喋らせたいことを誘導していますよね。真実過ぎても面白くないですし、全部嘘でもつまらない。ファッションでいうと、スタイリストの北村さんの仕事にその部分を感じますね。撮影前にハンガーラックで見る限りは、無茶だなと感じるような服でも、モデルに着せつける中でどこかに本当らしさと説得力を入れて下さるので、結果的にファンタジーとリアルの間にしか生まれない緊張感を演出してくれます。
親さんのその視点は、写真だけではなく他のジャンルの作品を見るときも通じていますね。
特に映画に関してもそういう目で見ていますね。どの設定に嘘を入れて、どこまで本当らしさを入れるのか。真実らしい部分が多ければ多いほど、フィクションの部分がどれだけ突拍子がなくても信じてもらえると思います。例えばクリストファー・ノーランの『バットマン』シリーズも突拍子もない話なのですが、バットマンの武器があり得そうな軍事品というところが、みんなが入り込めるポイントだったりしますね。写真もファッションも映画も、芸術の域に達したものはどれもそこをおさえていると思います。

Interview text_ SHINGO ISOYAMA