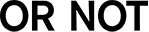REPURPOSE_RYOHEI KAWANISHI
廃棄されてしまうような“不要品”に新たな意味や目的を創造する、リパーパス・プロジェクト。
今回のプロジェクトのコンセプトを教えてください。
コロナ禍で利益を伸ばした会社と、労働者階級に関連する企業の衣服を集めて刺繍を施しました。象徴的な企業のロゴマークと刺繍の組み合わせというシンプルな構成です。

刺繍されている文言を選ばれた経緯をお聞かせください。
昨今の情勢は、格差社会をさらに拡大させつつあり、上流階級と下流階級が社会の中心になるといわれていますよね。そこから着想しました。今回選んだ文言には、諸説あるのですが有名なところでいうと、アメリカ合衆国のロナルド・レーガン大統領、ジョージ・H・W・ブッシュ大統領、イギリスのマーガレット・サッチャー首相などの任期中に、当時の経済的な傾向を解説する用語として頻繁に使われていたとされています。最近では、トマ・ピケティの本でも取り上げられていたみたいですし、古くは聖書のマタイによる福音書も関連しているという記述もありました。

今回使用されたボディの中には、ファッションの世界においてもラグジュアリーとされる企業のアイテムもあります。どのように集めたのでしょうか?
ほぼ全てオークションサイトで集めたのですが、例えばある一着には5万円ほど掛けてしまいました(笑)。原価は、300円くらいのアイテムから数万円のものまで幅広く集めました。
原価はアイテムによって異なるということですが、Tシャツとフーディーのそれぞれの商品単価は均等になっていますね。
衣服そのものに対する価値ではなくコンセプトに対しての値段を付けさせていただきました。幾らで仕入れたから幾らになるというシステムを壊したいなと。もともとは会社の一株あたりの値段から値付けしていこうと思ったのですが、あまりにばらつき過ぎるのと株を保有していない会社もあったので、定価は均等にしておきました。

一般的にアイテムのアップサイクルというと構築的な衣服が連想されると思います。一方、今回のプロジェクトでは衣服そのものにはほぼ手を加えていませんね。
そもそも構築された衣服は、個人的にあまり趣味ではないんです。それよりも見せ方の角度を変えることで全く別物に見えるような衣服の方が好みですね。最近、東京の街を歩いていて気付いたのですが、結局人類が行き着いたのは、Tシャツにスウェット素材のフーディーとパンツ、スニーカーの組み合わせなんだなと(笑)。これ以上、楽な服はないと思いますね。
では、ご自身で衣服を着られる際に意識されていることはありますか?
自分がお洒落をするのであれば、あの時代のこれとこの時代のこれを合わせるといった掛け算、引き算、足し算で構成するのが好きですね。ただ僕も最近は、自分のブランドとCARHARTTと民藝に関連するアイテムしか着ていません(笑)。

昨今のサステナブルに関する現象は、川西さんの目にはどのように映っていますでしょうか?
デザイナーは、作る側の人間なので地球からみれば僕らはみんな悪者なのだろうなと。ですので、僕らみたいな存在がいなくなれば環境にとても良いのではないかと思いますね。
そうは仰いますが、ご自身でサステナブルに関するプロジェクトも手掛けていらっしゃいますよね?
個人名義のプロジェクトでも一応は取り組んでいます。最近でいうと、僕の地元・鳥取で自動車のリサイクル事業を行っている西川商会とAIR GARMENTSというプロジェクトをスタートしました。西川商会で解体した車体からエアバッグを取り外し、鳥取県内の縫製工場でエアバッグの継ぎ接ぎのテキスタイルを作り、衣服に仕立て上げています。大量の産業廃棄物を再利用していくこのプロジェクトでは、僕らより前の世代の後始末をするというコンセプトが軸になっています。

2020年にニューヨークから故郷である鳥取に戻られてからすぐに、着物を再利用したブランド・LE FRAISを立ち上げられました。
そもそも、鳥取には生地屋さんがありませんでしたし、資金がないので他県の生地屋さんでも購入できる布の種類が限られていました。そんな時期にふと骨董市に立ち寄った際に目にしたのが、全てシルクでできた着物やかすり糸で作られた布など、自分では絶対に作れないような着物の生地でした。しかも、それがゴミ同然の値段で売られている。そこから着想してコレクション制作に繋げていきました。ただその当時、一番合理的な選択肢を取り続けた結果がサステナブルという現象に繋がっていったというお話で、当初からサステナブルを意識していた訳ではありませんでした。
川西さんのプロジェクトには、一貫して価値と価格を巡る既存のシステムへのアイロニカルなアプローチがあると感じます。そこに惹かれている理由は、どこにあるのでしょうか?
価値のないモノをどう価値付けしていくかには、昔から興味がありますね。それに僕自身がしたいことというよりも、その時々の環境や状況から逆算してゲームのように組み立てていくのが好きですね。難しいお題を投げられると、なぜか燃えてきてしまうんです。
Interview text_ SHINGO ISOYAMA
photography_ DAISUKE HAMADA
hair & makeup_ HAYATE MAEDA
model_ ANNA
NATSUMI TAKAHASHI
JAN URILA SAS