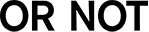TALKING ABOUT ARCHIVES Vol.19
アーカイブに見る、社会潮流とファッション -その時代だったからこそ、生まれたもの- 栗野宏文(UNITED ARROWS) (前編)
ファッションは社会と常に繋がっている、だからこそ面白い。知っているようで知らないこの結びつきを、アーカイブを通して探る企画。今回、話を聞いたのはユナイテッドアローズ上級顧問の栗野氏。バイイングをする際も必ず社会潮流を意識するという彼に、私物のアーカイブを通して年代ごとに語ってもらった。前編では、70年代~90年代までについて。

「ファッションは、“時代”があるから面白い」
--- 先ず、栗野さんがこの業界に入った70年代の話からお聞きしたいです。
「70年代は、ヒッピー思想の延長で、それこそサステナビリティという言葉はなかったものの、エコロジーという言葉はあって。地球との付き合いかたを世の中が考えだした時代なんですね。
その頃、ホール・アース・カタログという本があって。世界中のプロダクト好きや、日本の編集者に大きく影響を与えたんです。地球上で人間が生きていくためには何が必要かという内容で、地球と上手く付き合っていく為のプロダクトを紹介したのが、この本です。世界の多様な情報を入手することが困難だった時代にあって、とても貴重な本でした。

Right:ヒッピーカルチャー全盛の1960~1970年代の写真を集めたアートブック。
日本のファッションシーンでいうと、1976年に雑誌ポパイが創刊。本格的な山登りに使うヘビーデューティーな服を街で着ようという提案をしていました。今の若い子たちが、ノースフェイスやスポーツブランドを着ているのと同じ感覚ですよね。その時代に僕が購入したのがアウトドアメーカーの老舗、シエラデザインズのもの」。

「コットンが60%でナイロンが40%(通称ロクヨンクロス)のこのパーカは、ブランドを代表するモデルです。今ではもっと高機能な生地が沢山あると思いますが、その時代におけるハイテク素材。防水性、通気性、耐久性も高いということで、大変な人気でした。こういったアウトドアな服を当時はよく街で着ていました」。
--- 地球と向き合うという思想は、今の時代とかなり近いですねー。
「そうなんです。多分、その頃の思想が今にも続いているんだと思います。ただ、今はもっと切実になっていて。地球と向き合うという考えから、地球をどう守るかという動きに変わっています。
歴史を振り返ると第二次世界大戦が終わったのが1945年。その後、南北朝鮮による朝鮮戦争が1950年代に起こりアメリカも介入しました。その間、朝鮮特需といって日本国内の各企業に物資の発注が急増し、それで日本は戦後の不況を脱出できたと言われています。
50年代は、ロカビリーが流行って若者が社会の中心になりはじめ、音楽とファッションが融合。60年代のプロダクトは大量生産できるものが世の中に影響を与えた時代。アンディ・ウォーホルらが台頭し、ポップカルチャーが全盛となります。
70年代には、そうした大量生産時代に対する反省が表出していました。だからホール・アース・カタログみたいな本が出て、世の中の人が地球と向き合う時代になっていった。ファッションもその社会と並行して、アウトドアウエアを街で着るということは、地球について考えている証的にも捉えられて。“地球について考えて服を着るということがクール”とされていたニュアンスです」。
--- 80年代は、それがどう変わっていったのでしょうか?
「本物のデザイナーが沢山生まれた時代ですね。1986年前後にアントワープ・シックス(ドリス・ヴァン・ノッテン、アン・ドゥムルメステールなど)が登場し、1989年のコレクションでマルタン・マルジェラがデビュー。コム デ ギャルソン、ヨウジヤマモトも70年代からブランドはあったものの、パリでランウェイをやったのは、80年代ですよね。そういった意味でもデザイナーズファッションが盛り上がり始めたのがこの時代です。
あと、FACE MAGAZINE(1980年発行)とID MAGAZINE(1980年発行)は、世界を知るということにおいて、もの凄く僕自身も影響を受けた雑誌です。今では紙媒体の存在自体が問われていますが、当時はこれから雑誌が面白くなるという時代でした。この二つの雑誌は巨大資本から発行されている訳でもなく、インディペンデントで、面白いことだけを取り上げていた。どちらもロンドン発で、ファッションだけではなく、音楽、スポーツ、政治も網羅していましたね」。

Right:1984年~1991年の期間のみ発売されていた、CITY MAGAZINE。判型が大きいのも特徴で、世界中のカルチャーを発信していた。
「日本ではポパイが果たした役割が大きいように、世界で言えば、FACEとIDの功績は大きいと思います。所謂ストリートカルチャーと雑誌との距離が近かったのがこの時代の特徴です」。
--- 70年代の地球と向き合う時代から、80年代はまた一回戻って、もっとお洒落しようぜ!っていうムードになったんですか?
「80年代は分岐のディケイドで世の中全体が一括りではなくなるんですね。エコロジーを考えている人はずっとその先も考えているし、アウトドアやエコロジーは滅びたわけではなく、それはそれで1つの潮流としてこの時代にもありました。
例えば、60年代後半から70年代前半のヒッピー時代はメインがラブ&ピース発想だから、複数の人間が一つのことをメッセージする、“We”の時代。その後、音楽もファッションも“Me”の時代に少しずつ移り変わっていきました。シンガーソングライターが台頭したり、個人が個人のことを語る時代。考え方はそれぞれ違っていて良いという潮流で、FACEやIDにもそれが色濃く反映されていました。
CITY MAGAZINE(1984-1991)という雑誌もあって、オリンピア・ルタンの父親がイラストを描いていたり、まだ誰もバルセロナに注目していなかった時に、今バルセロナが面白い、などと紹介したりしていました。世界で起きていることを、どこか一つの国に偏らず同じ熱量でどの国も違った面白さがあると取り上げていたんです。この時代はストリートで起きていることと、雑誌で取り上げている速度が良い感じにシンクロしていて、早すぎす、遅すぎず…そこが心地よかった気がします」。
--- その頃の日本はどうでしたか?
「80年代の日本といえば、パルコの功績が大きいと思います。去年(2019年)渋谷のパルコがリニューアルして、皆さん称賛していましたよね。実はパルコは同じようなことを80年代に既にやっていたんです。当時の広告もとにかく豪華で。例えば、糸井重里さんのコピーや石岡瑛子さんのアートディレクション。アンディ・ウォーホル、ジェームス・ブラウンもパルコの広告に出たりしていました。いい意味でバブルの恩恵で、クリエイションにお金が動いた時代でしたね。だからMVにしても商業施設にしても面白いものが沢山ありました。
80年代は世界中でデザイナーが盛り上がったし、日本でいうとパルコがそれを売る場所として機能していました。一言でいうと80年代は“クリエイションの時代”でしたね」。

--- 90年代はサンプリングの時代とか、なんでもありの時代などと形容されますが、栗野さんから見てどうでしたか?
「バブルが崩壊した後の90年代は、コム デ ギャルソン、イッセイミヤケ、ヨウジヤマモトのようにクリエイションを研ぎ澄ませて生き残っていく流れがある一方で、クリエイションの方向性自体が変化して、シャビーなものやストリートよりになっていきました。より等身大のものがカッコイイとされました。80年代のバキバキのクリエイションとは逆というか。よりヒューマンスケールで、より人間っぽいものに流れていった。この服は、1993年-1994年秋冬のドリス ヴァン ノッテンのもので、その時代の気分を表していると思います」。

「この時のドリスのコレクションは、ベラチャオがテーマ。ベルナルド・ベルトルッチ監督の「1900年」という映画に影響されたようです。1900年頃というのは、未だ階級が強く分化していた時代ですが、ドリスは当時の貴族的豪華さを追うのではなく、逆サイドである労働者のシャビーな格好良さをコレクションにしたんですね。
これは3ピースのスーツなのですが、襟がワークウエアのようなデザインになっています。その頃はグランジが席巻していて、従来的な派手なファッションというよりは、シンプルなスタイルがクールとなっていきました。
日本だと1994年にアンダーカバーが設立されて、初めてのランウェイをこの年にやっていますよね。そういう意味でもストリートの空気を吸ったもの、音楽でもファッションでも高級に見えないもの、というのが、この時代の特徴ですね。
一方で、DJの時代でもありました。0から物を作るのではなく、カバーとかリミックスが台頭。エディティングすることが面白い時代で、僕らも1号店をオープンした1990年には、イタリアのスーツ的なものと、ドルチェ&ガッバーナ、チューブなどを一緒に売っていました。それは当時のリミックスカルチャーやエディティング思考の表れだと思います」。
栗野宏文/HIROFUMI KURINO
「UNITED ARROWS」バイヤー、クリエイティブディレクター、ジャーナリスト
1953年にニューヨークで生まれ、1977年に鈴屋に入社。ビームスを経て、1989年からユナイテッドアローズ創業メンバーの一人として活動。ユナイテッドアローズ上級顧問として活躍する一方、アフリカと日本を繋ぐプロジェクトFACE.AJのディレクターなども務める。
Photo_ RYO KUZUMA
Edit &Text_ TATSUYA YAMASHIRO