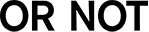TALKING ABOUT ARCHIVES Vol.20
アーカイブに見る、社会潮流とファッション -その時代だったからこそ、生まれたもの- 栗野宏文(UNITED ARROWS) (後編)
前編では、70年代~90年代までの社会潮流とファッションについて語ってもらった。その続編となる今回は、00年代以降のファッションと社会の結びつきについて。

「ファッションは、時代を先んじることもできる」
--- 前回は、90年代までについてお聞きしました。2000年以降のファッションはどうでしょうか?
「ファッションがしっかり市民権を得たのは90年代頃からだと思いますが、コマーシャル化したのも現実。一方で、コム デ ギャルソンや、イッセイミヤケ、ヨウジヤマモト、アンダーカバーなどは、よりコンセプトを重視していったように感じます。なかでもコム デ ギャルソンに一番特徴的なのは“ジェンダー”ですね。

このジャケットは、2012年-2013年秋冬コム デ ギャルソン・オム プリュスのもの。
シーズンテーマは、Neither Man Nor Woman.(男でも女でもない)でした。このブランドとしてジェンダーフリーの思想はもともとあったと思いますが、はっきりとコレクションで打ち出したのはこの時だったと記憶します。僕が購入したのも襟やポケットに施されたブレードや、見返しの切り替えなど女性的なディテールが特徴的です。パッと見はメンズのジャケットに見えるけど、メンズのセオリーとは異なるところが面白いですよね。

2019年6月に発表された2020年春夏のコム デ ギャルソン・オム プリュスは、小説家のヴァージニア・ウルフが1928年に出版した「オーランドー」がテーマ。オーランドーという男性が400年間生きて、やがて女性になり、子供を産んで母親になって、作家になり成功するというファンタジー小説です。ウルフは元祖フェミニスト作家とも言われている人で、この小説は映画にもなっています。
その時のコレクションは、まだ男性だったオーランドーに女性の感覚が入っている状態を表現したもの。ジャケットにコルセットぽいディテールが入っていたり、ドレープやフリルが施されていたり、いわゆる男性物と女性物が入り混じったデザインが特徴です。
その後、2019年9月に発表したウィメンズはオーランドーが女性になった状態を表現していました。そしてコレクションが1部と2部だとしたら、その第3部がウィーンのオペラ座でした。
僕もその公演を観に行ったのですが、ウィーンのオペラ座が150年の歴史上初めて女性の作曲家に依頼したのです。その作曲家はコム デ ギャルソンがもともと好きで、ウィーンのオペラ座を通して川久保さんに衣装を頼んだそうです。川久保さんはその話をもらった時に、世界一のオペラ座が150年間一度も女性作曲家に依頼していなかったというところに、心を動かされたそうです。オーランドーの物語を通してジェンダーフリーをカタチにする究極のケミストリーだなと思いました」。
--- 面白いですねー。2012年-2013年秋冬コレクションから繋がっている、壮大なストーリーのような。
「そうですね。そして、2020年秋冬のコム デ ギャルソン・オム プリュスになると哲学的な内容ではなく、真直球なカラー・レジスタンスというテーマのもと、色や柄のぶつかり合いが印象的でした。
この変化は着る人に何を要求しているのか?と考えた時に、2020年春夏が男とか女とか言っている時代は終わった…という宣言だとしたら、2020年秋冬は、服に負けず、強さを持った人間であってほしい、というメッセージとして僕は受け止めました。
川久保さんって言葉では表現しないけれど、常に時代を考える人。それと同時に、世界一のコンセプターだとも思います。例えばトランプ政権で自由が奪われていく一方、ジェンダーフリーは社会的にどんどん進んでいる。メゾン マルジェラも男女合同のショーをやっていましたよね。そういう時代を感知して、そこに服でぶつけてくる感じです」。

--- コム デ ギャルソンのように常に時代を捉え、そこにメッセージを持っているブランドがずっと残っていく。
「単に可愛ければ、格好良ければ、それでいいんじゃない?というブランドには惹かれませんし、人の心を打たないと思います。決してジェンダーフリーだけが重要という訳ではなく、今の時代をどう捉えていて、今の時代とどう呼吸するかが大切であって。そういうブランドが結果的にずっと残っていっているように感じます。
服はリリースされた瞬間から過去化され、アーカイブともなりますが、それを語る際に、何年かおいて俯瞰で見ると時代背景が分かりやすく出てきます。その時代だからこそ生まれたものというのは確実に存在するし、いつの時代も色褪せないブランドというのは、そのような奥深さを必ず持っていて、アーカイブとしても残っていくのだと思います」。
--- これからファッションの未来はどうなっていくと思いますか?
「青山のコム デ ギャルソンで、ミキモトとコラボレーションしたパールのネックレスがマネキンにかけてありました。それも、ただのマネキンじゃなくて生々しいマネキンのモールド(原型)。この生々しさが今後注目されていくんじゃないかと思います。宝石は地球の堆積物に由来しますが、真珠とサンゴは動物由来。その動物を身につける行為って凄くシャーマニックだなと思うんですね。亡くなった方の口に真珠を置くしきたりもあったり、昔は真珠を粉にして飲んだりもしていたようです。日本では葬式や結婚式にも身につけられる唯一のジュエリーですよね。生と死にまたがる装飾品。
イブラヒム・カマラの様なアフリカのクリエイターを見ていてもそうですが、シャーマニズム的なことがファッションにとって重要になっていくのだと思います。洋服とは本来その日の気分を表すメンタル的な部分が多かった…それが過去数年間は、ロゴを自慢するとか、並んで買ったものを見せびらかす、といった即物的なものになっていった。今後はその反動が大きくなっていくと思います。古代のように装うことで神と繋がる、とまでは言わないけど、自分の存在を強くしてくれるものであり、それを隠してくれるものでもある。それがファッションの魅力ですよね。ファッションは今生きている時代の気分を表すと同時に、“時代を先んじることができる”。だから面白いんです」。

栗野宏文/HIROFUMI KURINO
「UNITED ARROWS」バイヤー、クリエイティブディレクター、ジャーナリスト
1953年にニューヨークで生まれ、1977年に鈴屋に入社。ビームスを経て、1989年からユナイテッドアローズ創業メンバーの一人として活動。ユナイテッドアローズ上級顧問として活躍する一方、アフリカと日本を繋ぐプロジェクトFACE.AJのディレクターなども務める。
Photo_ RYO KUZUMA
Edit &Text_ TATSUYA YAMASHIRO