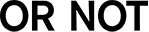INTERVIEW WITH FIONA STUART / RELLIK
ロンドンの老舗ヴィンテージショップ創設者にインタビュー
デザイナーズヴィンテージの価値と熱狂は年々増すばかりで、今やヴィンテージを取り扱う専門店は数え切れないほど世界中に点在する。しかし2000年以前、そのいくつが存在していただろうか。1999年12月、ウェストロンドンのポートベローマーケットで偶然出会い、友人になったフィオナ・スチュアート(Fiona Stuart)、クレア・スタンスフィールド(Claire Stansfield)、スティーヴン・フィリップ(Steven Philip)の三人は、有志で小さな店「Rellik(レリック)」をオープンした。
今でこそ新進気鋭デザイナーやアーティストがスタジオを構え、コミュニティを形成するのはイーストロンドンだが、当時のノッティングヒルはいわゆるヒップなエリアだった。アート学生たちがコーヒーショップでデザインについて語り、ミュージシャンたちがお酒を飲む社交の場。今の観光地化した姿からは想像できないが、まさにそんな場所だったのだ。しかしクリエイティヴの聖地ですら、当時のデザイナーズヴィンテージに対するマーケットは非常にニッチで、多くの人はもっぱらスウェットシャツ、トラックスーツ、スニーカーなど、デッドストックのスポーツウェアに夢中という流れ。セカンドハンドの方がよっぽど人気があった頃。店を構える以前、三人は周囲から「そんなビジネスは成立しない」「美術館に飾るような古臭い洋服を売るなんてどうかしてる」といった辛辣な言葉を投げかけられたという。
それから20年以上が経過し、ロンドンのヴィンテージストアの中でもRellikは有数の店へと成長した。オープン時から変わらず足を運ぶ常連客から、スタイリストやセレブリティまで、多くの層から愛され続けている。
店内には60年代から現代まで数々の名作が並ぶ。Comme des Garçons、Issey Miyake、Yohji Yamamotoといった日本を代表するデザイナーに加え、Alaïa、Ossie Clark、Courrèges、Bill Gibb、Thea Porterなどといった、今では美術館に展示されるような伝説的ブランドも少なくない。他にもYves Saint Laurent、Vivienne Westwood、Thierry Mugler、Helmut Lang、Jean Paul Gaultier、Ann Demeulemeester、Balenciaga、Celine、Martin Margielaといった現在も人気のブランドも多数ストックしている。
クレアとスティーヴンの二人は今年に入り、長年続いた三人での“結婚”生活に別れを告げた。前者はアートの道へと進むため一時的な休暇に入り、後者はブライトンへ移住、コンサルタントとアポイントメント制のアーカイヴストアを始めた。それぞれが異なる道へと進み、フィオナだけがRellikに残ったのだ。大衆がヴィンテージへと目を向けるよりも前から今日まで、ヴィンテージと人生を歩んできた彼女だからこそ分かることとは。
ファッションに興味を持ったきっかけを教えてください。
小さい頃からファッションに夢中でした。オーストラリアのキャンバーウェルで育ったんですが、周りには好きな洋服を買えるお店がありませんでした。そこで自分で生地を買ってきて、パターンを引いて、洋服を作っていたんです。そういうことをしばらくずっと続けていて、15歳のときに父の転勤をきっかけにロンドンに引っ越してきました。私にとってイギリスは70年代が洋服、80年代が音楽の黄金期。特定のアーティストやミュージシャンではなくて、ムーヴメント全体やクラブカルチャーが大好きでしたね。それ以来、ポートベローマーケットの近くに住んでいるので、マーケットにはよく足を運んでいました。
ファッションやデザインを勉強されていたのでしょうか?
1988年にCentral Saint Martins(以下CSM)でファウンデーションコースを修了した後、Kingston University Londonでインテリアデザインを学びました。CSMで学んだのは(ジョン・)ガリアーノたちが在学していた少し後だったんですが、それでも80年代のCSMは素晴らしかったですね。授業初日のことは未だに覚えています。外に急に連れ出されて、落ちているものを拾って、それらを用いてアートワークを作ることが課題でした。それにレクチャーはいつもパブでやっていました(笑)。先生たちはいつもビールを飲んでばかりで。今とは違って学費が政府から補償されていて、金銭的なプレッシャーがない状態で純粋にファッションやアートを学ぶ機会があり、すごく恵まれていたと思いますね。



卒業後すぐにRellikをスタートさせたのでしょうか?
卒業してからはしばらくインテリアデザイナーとして働いてたんですが、あまり仕事がなかったんです。そんなとき、家の近くを歩いてたら「一緒に働かないか?」と声をかけられて、マーケット内のストアに立つことに。それから数ヵ月後には自分のストアを出店していましたね。最初は、デザイナーが作ったサンプルやファーストコレクションを売っていました。サンプルを作るのは膨大な時間と労力がかかるし、時にはサンプルの方が希少性もあって面白い洋服ができるんです。ファッションやアート学生が制作する卒業コレクションもありましたね。でもポートベローの人たちは古着が好きだったから、そのビジネスは全然上手くいかなくて、一週間でやめました(笑)。次の日から、自分のワードローブにある洋服を売り始めたら、それが軌道に乗って、結局5年くらい続けましたね。日本人のお客さんもたくさん来てくれていて、Ossie ClarkやBIBAなど、70年代のものをたくさん買っていってくれました。その後、マーケットだと冬は寒いし、トイレに行くのも大変だから、どこかにベースを構える必要性を感じて、隣のストアにいたクレアをまず誘って、もう一人くらい必要だったからスティーヴンにも声をかけました。元々コンビニがあった物件だったんですが、家賃も高くなかったですし、良いスペースだったので即決断しましたね。それがRellikの始まりです。
当時のロンドン、特にウェストロンドンのファッションやカルチャーを取り巻いていた様子を教えてください。
とにかくエネルギーに満ち溢れていました。ウェストロンドンは今のハックニーみたいな雰囲気で、若者たちがたくさんいて、活気のある楽しくてクールなエリア。そこにはカルチャーが存在していましたね。『ノッティングヒルの恋人』が公開されてからは家賃の高騰と開発が進んで、どんどんケンサルライズの方に人々が流れていきました。その頃から、この周辺はキャラクターを喪失してしまったように感じています。
Rellikが他のヴィンテージストアと違うのはどんなところでしょうか?
しっかりとした歴史と価値があり、なおかつ今でも着られるものがあること。「モダンヴィンテージストア」と形容できるのかもしれません。さらにRellikはお客さんとの距離が近く、長く通ってくれている人が多いのも特徴。ふらっと立ち寄って、色々と試着して買っていってくれるんです。それから少し経って「この前のあれがすごく良かった!」と言ってまた戻ってきてくれるんです。それはすごく嬉しいことですね。


ご自身のお店以外に、お気に入りのヴィンテージストアを教えてください。
ロンドンでは行きませんが、海外旅行をするとやはりヴィンテージストアに足を運びます。洋服とカルチャーは結び付いているので、国によってもお店の感じは当然変わってきます。ヴィンテージに対する考え方や視点も違うと思います。具体的に挙げるとすれば、バルセロナにあるLe Swingは良かったですね。もちろんパリやニューヨークにもたくさん素晴らしいお店があります。
時代の変化とともに、客層などは変化しましたか?
お店をずっとやっていると、長年通ってくれているお客さんの子供や、若い世代の子たちが来てくれます。そうした光景を見ているのは楽しいですね。私の年代の人たちは外出する機会が減り、さらにボディサイズが変わるので、洋服を売りにきてくれます。反対に10代や20代の子たちはヴィンテージに新鮮さを感じているみたいで、どんなものでも着てみますし、他の人と違う格好をしたいというのが分かりますね。特に90年代のものが人気です。




昨今のヴィンテージに対する熱い視線は、懐古的というよりも流行的側面が強いように感じます。長年ヴィンテージストアを経営してきたあなたは、この流れをどのように見ていますか?
今はヴィンテージの価値が上がり過ぎていると感じます。洋服を売りに来る人の多くも、高額な買い取りを期待していますね。ヴィンテージの洋服の値段なんて、結局は買い手次第で決まるものですし、洋服はアート作品ではありません。確かに洋服も価値はありますが、ダミアン・ハーストのアート作品とは違います。スニーカーに数千ポンドも払って、履かずに飾っておくなんて馬鹿げているなと……。以前、カール・ラガーフェルドがデザインしたSteiffが発売されて買ったのですが、飾っておくだけのがおかしく思えて、結局は売ってしまいましたね。あと、ヴィンテージの洋服は価格が高騰していっているだけではなくて、同時にノスタルジーさを求めている人も多いと思います。昔のYves Saint Laurentが好きな人もいれば、Paco Rabanneが恋しい人もいます。歴史があるオリジナルのものには大いなる魅力があるものです。同じブランドでも、デザイナーが変わると訴えてくるものが違いますし。
デザイナーが交代するとブランドも変わると?
メゾンはデザイナーが離れたり亡くなったりすると、なぜ代わりのデザイナーをすえてまでして継続するのか、理解に苦しみます。そうすることで新しいデザイナーが出てこないですし、皆結局どこかのブランドでデザイナーとして働くケースばかりです。ブランドはデザイナーを起用するよりも、デザイナーのスポンサーをすべきだと思いますね。昔、Hyper Hyperという若手デザイナーを支援するお店がケンジントンにあったんですが、もっとそういうスペースやお店が必要です。昔はBrownsが学生の卒業コレクションを買ってウィンドウディスプレイしたり、Dover Street Marketも若い才能を支援したり。イザベラ・ブロウがアレキサンダー・マックイーンのコレクションを購入したのも有名な話ですよね。


昔からずっと好きなデザイナーはいますか?
マルタン・マルジェラは間違いなく好きなデザイナーの一人。ファッションを通じて自分がやりたいことを見事に表現していたと思います。マックイーンもそうですよね。両者とも、単に人間が着る物体をデザインしていたのではなくて、生きているものを生み出していたと思っています。洋服やコレクションを作る枠組みの外でデザイン活動するデザイナーはなかなかいません。Yves Saint Laurentのデザインも、どれもタイムレスで美しいピースばかりです。
日本人デザイナーの特徴があるとすれば、どんなものでしょうか?
シェイプですね。丁寧にテーラリングされているだけでなく、着やすく、フィット感も美しい。素材も最高レベルで厳選されています。デザイナーの多くは注目を集めるために毎シーズンスタイルやテーマが変わるりますが、日本人デザイナーたちには継続性があるんです。川久保玲や山本耀司のようなデザイナーたちは、ブランドを始めた当初から一貫しているものがあります。それだけでなく、毎シーズン新しいことを実験的に模索しているんです。70年代のISSEY MIYAKEやKENZOも大好きですし、デザインに対する冒険心を強く感じます。世界中のデザイナーたちがインスピレーションのために、日本人デザイナーのヴィンテージアイテムを買っていきますからね。








COVID-19や環境問題など、社会的に大きなシフトが求められている中で、ファッションが担う今後の役割はどんなものなのだとお考えですか?
ファッションには、常に人の気持ちを高ぶらせる力があると思っています。自分の身体を覆っているわけですから、すごくパーソナルなものですよね。安心や暖かさ、それに加えて自己表現のツールでもある。だから今後、ファッションはより消費物としてではなく、いかに人を幸せにできるものであるかを考える必要があると思います。今は世界中で大きなシフトが起こっていて、停滞したムードが漂っています。おしゃれをして出かけることもできないですし、そうした日々がいつ戻るのかも分かりません。そんな中、Isabel Marantが発表した2021年春夏コレクションは最高でした! パーティやディスコがテーマになっていて、モデルたちが楽しそうに踊っていたんです。いつか世界が正常な状態に戻ったとき、こういう服が着たいって思わせるようなショーでしたね。これからは楽しくて幸せな洋服が求められていくと思います。
こういった状況下で、一番の楽しみは何ですか?
以前はエキゾチックな場所に旅行するのが楽しみだったのですが、規制のある“小さな世界”での生活だと難しいですね。最後に行ったのはジャマイカ。今はガーデニングと犬の散歩、料理、ヨガ、水泳をするくらい。高校生の娘がいるので、基本的には仕事と家の往復。オックスフォードにあるBlenheim Palaceでやっていたセシリー・ブラウンのエキシビションは良かったですね。私のほかに4人しかいませんでしたが、もしかするとそれが本来あるべき姿なのかもしれません。そこで気付いたのは、どれだけアートが恋しかったかということ。気付けば、最後に行ったのは2月、Tate Modernで開催されていたアンディ・ウォーホルのエキシビションでしたね。
お店にもウォーホルのプリントが飾られていますが、好きなアーティストの一人ですか?
実はそうでもないんです(笑)。本来はルシアン・フロイドやフランシス・ベーコンのようなペインターが好きですね。彼らの作品は何時間観ていても飽きません。ゴッホがイギリスに住んでいた時期に描いた作品も素敵ですね。ロンドンでは色々なエキシビションが開催されるから恵まれていますけど、今は全てに予約が必要で……。

今現在のご自身のワードローブについてお聞かせください。
昔は70年代のドレスや、自分でカスタマイズした洋服を着ていましたけど、歳をとると感覚も変わりますね。今はRick Owens、Haider Ackermann、Preen、Yves Saint Laurentなどの洋服に、チャリティショップで買ったZARAなんかもミックスしています。
最後に今後のRellikとしてのプランを教えてください。
ロックダウンになってから、ウェブサイトにEコマースの機能を追加したんです。そして次はメンズウェアを始めるかもしれません。メンズウェアでワクワクするようなピースを見つけるのは難しいんですけどね。ヴィンテージストアで買い物をする男性は、女性と比べると断然少ないですし。あと最近はメディアへのリースも多くなってきましたね。ただ何より、世界中にいるお客さんたちに一刻も早く会いたいと願っています。





Text_ Takaaki Miyake