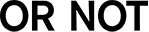INTERVIEW WITH KUNIHIKO MORINAGA
ANREALAGE森永邦彦が語るアーカイヴ。AとZは隣り合わせだった。
18年間のブランドヒストリーの中から、ANREALAGEが自らのアーカイヴから厳選した一着をOR NOTで販売することが決まった。千万無量の手仕事によって生み出された一点ものを含むコレクションピースと、過去のコレクションから得ることができているという新たなコレクション制作の手掛かりについて話を聞いた。
今回OR NOTでの取り扱いが始まるANREALAGEのアーカイヴピースを一望すると、森永さんがたびたび口にされる「神は細部に宿る」というセンテンスを再確認する思いになりました。そのアティチュードを貫く、原体験があればお聞かせください。
ブランドをはじめて18年が経ちますが、始まりはパッチワークにあります。19歳で服作りを始める時、自分の武器になるものがひとつもありませんでしたし、洋服自体を作る技術もなく、テキスタイルをつくる資金もなかった。その環境下で、自分ができることを模索しながら、何かで差別化するにはどうしたらいいかと考えあぐねた結果、持て余すほどあった「時間」、そして、人が縫うものよりも「細かいもの」を手掛けることに向かっていたんです。例えば、洋服一着を20パーツで作られるところを、100、500、1000パーツで作ろうとどんどん細かくしていく。数が膨大になればなるほどひとつのパーツは小さくなり、必然的に縫う時間がかかってくる。そうして、人が簡単にはたどり着けないところ、いわゆる「細部」といわれるものをとことん作ろうというのが、ブランドの原点にあるのです。


「細部」の捉え方は、18年間の中で変わってきましたか?
後にパッチワークを離れ、造形のシーズンにうつってはひとつのボタンをデザインし、テクノロジーを活用するシーズンで一本の糸をどういった色素を組み合わせていくかという部分をクリエイトすることが、それぞれのコレクションや洋服を作るはじまりになっています。つまり、細かいと思われる部分で、新しいことをどれだけやれるのかが僕たちのアイデンティティになっているのです。
ブランド名は「日常(real)」と「非日常(un-real)」、「時代(age)」の言葉を組み合わせた造語ですが、「細部」への注目とも関わり合っているのですか?
そうですね。非日常を、日常の中で気づかずに通り過ぎてしまうものだとずっと思ってきました。そうしたものは、すごい小さいものであったり、ボタンのようなもの、捨てられてしまう布きれであって、得てして『細部』と呼ばれるものが多い。そうした非日常なものを、ファッションを通じて作り上げたいという信念でやっています。そこにこそ自分たちが求める価値があるという気持ちですね。
ブランドの始まりは何名だったのですか?
本当の最初は1人ですね。当時は、渋谷のTOAという生地屋さんでバイトしていました。購入されたテキスタイルをカットしていたわけですが、お客さんが、大きくカットし過ぎたものや、小さすぎる端切れを捨てていたんです。そこで、毎日捨てられるものだけでも貰えないかと店長に相談したら快諾してくれて、お客さんにとっては不要だったテキスタイルが、必然的に僕の家に溜まるようになっていったんです。長い距離を縫ったり、曲線を縫うことはできなかったので、何度も何度も5センチくらいの直線を縫うということをやっていたらパッチワークができ上がったわけです。とはいえ、自分ひとりで一点ずつ作っていると、あっという間に1ヵ月が経ってしまい、なかなか量産することもできなかった。そこで、中学からの同級生の親友が、レンタルビデオショップでアルバイトをしていたのですが、DVDの波に押されて店が潰れ、職を失うタイミングだったので、「俺でもできたから縫ってみない?」と声をかけたんです。彼は、ファッションにまったく興味がなく、パンクやハードコアの音楽ばかり聴いていたのですが、それから20年間、ANREALAGEのパッチワークはずっと彼がやっています。最初は200パーツくらいで、それがだんだんと2000パーツになり、ひとつが1センチにも満たなくなってくる。この最初期のものも、いつかOR NOTさんに出したいですね(笑)。


今回、出品されるものについてお聞かせください。2007年秋冬コレクション「ハルカハル」で発表された10000個以上の多種多様なゴールドのボタンが使用されているジャケットについて。重量は10キロを越えるそうですね。
コレクションの一体目の服で、制作に3ヵ月くらいかかりました。「神は細部に宿る」ということを標榜しながら、パッチワークの次に、洋服において人々が目を向けていないものを思索していた頃に思いついたのが、あくまで「付属」という言葉がつく小さなボタンでした。ボタンだけで洋服を作りたいと思って制作したもので、装飾としては激しく、印象はかなり強いと思います。このシーズンでやりたかったことのひとつとして、モデルが着て歩くときに発生するボタン同士がぶつかりあう音が、まるで洋服の声や叫びのようだという解釈を強く打ち出したかったんです。来日したレディー・ガガが着たいと連絡をくれて、この金ボタンのものは実際に着用されたものですね。


3ヵ月間の制作はどのように進められたのですか?
アトリエ内に置いておいて、スタッフ全員で少しずつボタンを付けていきました。コレクション当日が迫ってくるにつれて徐々に完成していくという、カレンダー的な役割を果たしていましたね(笑)。
このピースも含め、今回の出品を決めた理由を教えてください。
異常な量のボタンを付けることが自分たちの原点になるかどうかもわからないような気持ちでやっていたのですが、「ハルカハル」のシーズンは自分の原風景をコレクションで発表しようとしたものでした。そこからちょうど12年が経ち、「ハルカハル」を自分なりに英語に訳したコレクションをパリで発表したのですが、自分が立ち返る場所がずっと晴れていて欲しいという願いを込めて「CLEAR」としました。フォトクロミックの技術を使って黒い物体が透明になることにフォーカスしたコレクションですが、実はショーの1体目が「ハルカハル」の1体目と同じように、後に透明に変わる無数の真っ黒なボタンをつけて、歩くとジャラジャラと音が鳴るというものだったんです。現在のANREALAGEを知っている方々は、ボタンの色が変わること自体の印象が強いんですが、自分たちとしてはその原点が12年前にあり、今のコレクションが生まれているという認識の方が強い。これまでいろいろなテーマをやってきているんですが、中心にあるのは「日常を非日常に変えたい」という願い、「非日常を日常に変えたい」という祈りです。今回のピースには、僕らにとって魂のような洋服が多いので、そうしたブランドの思考を強く感じてもらえるのではないかなとも思っています。短期的な視点だとわからないことも、現在のコレクションともつながっている何かがあるのだと感じていただき、より理解していただけるとブランドとしてすごく嬉しいですし、そうしたことを象徴するピースをOR NOTさんに出品させていただこうと決めました。
次のピースについても伺いたいです。2007年春夏コレクション「祈り」で発表されたジャケットもまた、約5000個のボタンが縫い付けられた一点ものです。ボタンのほかに、パールやクリスタルも含まれています。
このジャケットは「祈り」のラストルックなのですが、実は、次のシーズンである「ハルカハル」と同じマインドを共有した連作なんです。当時の東京の中で、どこよりも一着に対して手を動かして作ろうという野心のような思いがあり、まっさらな白いジャケットに装飾を付け加えていく作業を続けていると、その行為が何かに祈るような気持ちで服を作っていることに気づいたんです。パールやクリスタルと、付属品であるボタンは、もともとの価値も値段も違いますが、手作業によって並列なものとして置き換えられていきました。このシーズンで忘れ難いのは、無名の僕たちの服が『WWD』の表紙になったことですね。もうこれはやらないといけない、作り続けなくてはいけないと、覚悟を決めたことを覚えています。


花柄のゴブラン織りのテキスタイルをパッチワークしたジャケットは、これまでご紹介いただいたピースよりも比較的最近で、2019年秋冬シーズンに発表されたものです。ほとんどのコレクションで原点であるというパッチワークの手法は貫かれていると思いますが、初期からの違いはありますか?
もともとは資材として用いられ、カーテンやクッションに使用されるゴブラン織りのテキスタイルから花柄の部分だけを抽出して、1500パーツくらい貼り合わせたダブル仕立てのピーコートですね。初期の手法はかなりアンコントローラブルで、パッチワークの安定性はありませんでした。パーツも、細長いものもあれば、いびつな四角や三角があったりする。2019年秋冬のものは、計算はしていませんが、計算されたような表情をしているかもしれませんね。当初からずっと追い求めているのは「パターン化しない」というルールで、具体的には1500パーツが一つひとつ違う形をしていなくてはいけないという決まりごとだけがあるんです。最近の、三角のパーツをベースにした服でもすべてのパーツの形は違う。同じように見えて差異を出していくという、実はすごくテクニカルなことをやっています。
2013年に発表された、カラフルなステンカラーコートもまたパッチワークですね。
細部に対する考えは一貫していますが、通常のパッチワークだと素材はせいぜい10種類くらいなところを大幅に超え、100種類以上のテキスタイルを使うという、ある種の多様さを表現している一点です。
ここでご紹介いただく最後の一点は、2013年秋冬コレクション「COLOR」で発表された、紫外線にさらされることで色が変化するグレンチェックのジャケットとスラックス。フォトクロミック技術を活かしたテキスタイルで仕立てられたものです。
洋服の実物そのものの色が、太陽の状況や天候によって完成するという洋服なので、一着を構成する大切な要素でもある色の概念を持っていないのです。糸の原料となる色素を国内の取引先と研究開発し、それを固形物にして、射出成形で繊維をつくっていきます。この服の特徴は、人がいつ、どこにいるかで色が変化することにあります。例えば、12月の東京の空の下で見ると緑っぽく見えるんですけど、半年先の梅雨時期の太陽だと紫外線量が違うのでダークグレーのように変化する。それが今後、また世界中を移動できるようになって、フランスで見たり、アメリカで見たりすると、ダークグリーンやカーキに変わっていく。時期と環境によって色が決定されるので、絶対的なものがない、移ろう面白さを人が着て初めて感じられる洋服です。自由に人が移動できたり、外に出られたりする日に向けた願いも込めて、この服を面白く着られる日がまた来るといいなと思っています。また、これと同じ技術を使ったものが、FENDIとコラボレーションしたものとして発売になりますが、FENDIとしても珍しいメイドインジャパンで糸を生産する理由は他の場所ではできなかったから。すでに7年以上も色の移ろい方やヴァリエーションの研究を重ねて、当初に比べたら格段に進化してきました。が、新しい技術はすぐに成熟しないので、一度足を踏み入れた以上は十年単位での覚悟をもってやらなきゃいけないと思っています。


ご自身のパストワークを振り返っていただいているわけですが、アーカイヴとはどのようなものだと捉えていらっしゃいますか?
例えば、2007年に洋服を全力で作ってコレクションとして発表したら、「次」に向かってどうしてもそこから離れたくなってしまって、もうみるのも嫌なくらいになっていたんです。過剰なまでに足し算ばかりした後は、一切手を動かさない造形のシーズンに移り、ある程度コレクションを重ねると、道具をいかに使うのかという命題に移行していったわけです。これまで、過去の手法に戻ることはないと思っていましたが、最近、特に「CLEAR」(2019年春夏)くらいから、「ハルカハル」や「祈り」への回帰であったり、翌シーズンの「DETAIL」では、細部を拡大して、球体、三角錐、立方体に合わせて形づくったシャツやトレンチコートを制作した「◯△□」(2009年春夏)への回帰があったりするんです。僕自身の考え方として先に進もうと強く思っているし、前進したずっと先に自分たちのアイデンティティがあると信じている一方、それが、ずっと以前にやっていたものの中にあって見過ごしているんじゃないかと思い始めているんです。アーカイヴというと自分がいる現在地から後ろにしか見えないと思いがちですが、僕は今、あえて迂回しているんじゃないか。アーカイヴを後ろではなく、先にあるものとして捉えることができたら、すごくいいなと思っているタイミングなのです。2021年春夏の「HOME」というコレクションは、文字通り、戻ってくる場所、原点回帰することができるというのが裏のテーマでした。コロナ禍で、進むことを一瞬でもためらい、立ち止まったタイミングでもあったので、価値を考え直す上で、新しさと古さの時間軸を取り除いて向き合うことができた。まだ適切な言葉が見当たらないんですけど、これから時間が経っても僕が今お話ししたところの「後ろ」になっていかないものを作っていきたいと思っています。




過去のシーズンのテーマを含めたアーカイヴを捉え直すことも、現在のANREALAGEのコレクション制作の一端を担っているということでしょうか?
「HOME」を制作している時に、アルファベットの「A to Z」の構造について考えていました。Aが始まりで、Zが終わりだとしたら、シーズンを重ねるごとに、だんだんとZに向かって進んでいるんだと感じていたわけです。一方で、その「to」が単なる直線じゃなく、グルっと回転するようなものなら、Zまでたどり着くと、隣にはAがあって、そこから2周目に突入していく。そんな心境になっていたんです。自分たちが通り過ぎたところをもう一度歩む中で、ブランドのコンセプトと同じように、拾い上げたいものがたくさんある。これ以上ないと思っていた「◯△□」のコレクションを、ただ少し大きく変換することで服の役割から住居的役割になりうるかもしれない。今までとは違う、球体や三角錐になるかもしれない。もう一度巡って、初めて気付くことだったし、その過程で、手仕事や身体性、テクノロジーの活用といったブランドのアインデンティティにも、今一度、向かい合いたいと考えています。





interview text_ TATSUYA YAMAGUCHI